―2009年4月、私は恋に落ちていた。
ただ、「恋に落ちる」という表現は
相手と私と二人でする行為であるようにも響くので断っておくと、
これは私の片想いでしかない。
それも、ディープで途方もなく絶望的な。
ある一人の男が。
ある一人の男が、私をいとも簡単に奪い去った。
本屋の棚の上で。
 菊地成孔『スペインの宇宙食』(小学館文庫)
菊地成孔『スペインの宇宙食』(小学館文庫)
のことをそろそろ書かねばなぁ。
出逢いは、そう本屋だ。
すべらかな、まるで象牙のような、
しかしライトパープルも含んでいるのか、さえざえとした表紙に
「スペインの宇宙食」と書かれている文庫が目に入った。
美しい装丁だ。作者は知らない。
手に取りたいという欲求は止められず、いつの間にかページをめくっていた。
日曜日の午前10時半、小さな本屋の隅での邂逅。
目に飛び込んできたのは、饒舌にジャンプアップする文体だった。
「美文」という語が耽美を褒める(または貶す)ためだけにあるのではないとして、
彼のそれは明らかに私にとっての"美文"であり、
しかしその美しさは不健康極まりない。
溺れる以外の選択肢はないような。
彼がどんな人間で、何をしている人でなんて知らなくていい。
その文体はすでに、私を揺り動かし、突き動かしていた。
ゆっくりと激しく。
その後、彼が音楽家であることを知り、
(3年ほど前から私は"音楽家"の書く文章を好んで読んでいる)
ちょうど来週、ライブツアーでこちらに来るらしいことが分かった。
5月1日―菊地成孔×南博のライブ「花と水」  に行く。
に行く。
ライブの終わりに、第二作目のエッセイ・評論集(『歌舞伎町のミッドナイト・フットボール』)にサインをしてもらった。
いつの間にか夏の日は暮れていて、
紅黒の闇を背景にして彼は「懐かしいねこの本」と苦笑した。
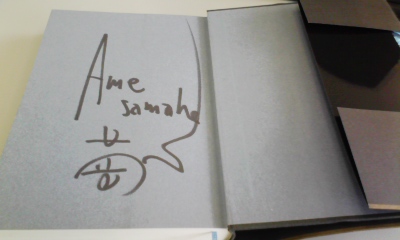
そして。
彼はサインする際いつもそうしているらしいのだが、
本を開いてページに香水をふりかけてくれた。
テュエリー・ミュグレーの「エンジェル」 
薄いブルーの星型の瓶。
暗い部屋の中、彼の手に握られたその星は発光しているようだった。
スパイシーな石鹸。
「淫らさ」と「清潔さ」は反する語ではないことを堂々と証明してみせた
色気あふれる鋭く艶のある香り。
ページを開くたび、彼の匂いがする。
ただ、『スペインの宇宙食』のあとがきにおいて言及されているように、
この本に閉じ込められた物語―それを書いた人物は
すでにもう、「ない」。
様々な理由によって。
過ぎ去りし青春とでもいうか、
痛みの季節を越し、振り返って懐かしくなるくらいの
思い出話になっている。
彼は「あの頃はもうない。君の愛しているものは、もうないんだよ」と、
今までに何人も諭したであろう慣れた口調で、しかし哀しい目をして私に告げた。
あと何回読み返せば、彼を忘れられるだろう。
私の本棚からは、まだ彼の匂いがするというのに。
