
|
|
|
カテゴリ:そこいらの自然
☆ 8月11日(水曜日) 旧七月二日 癸巳(みずのと み) 友引:
前回は上野公園のアブラゼミについて書いた。 セミの仲間は全世界で約三千種類も確認されているそうだ。大きいものは小鳥ほどにも大きい、十数センチにも及ぶのが居るらしい。小型のものは2センチくらいと「外米」程度の大きさしかない。同じ仲間とはいえ、大から小まで随分のバリエーションがあるものだ。 セミは不完全変態をする昆虫だ。つまり卵から幼虫、幼虫は何度かの脱皮を繰り返して、その後成虫になる。成虫になる前に蛹を作る、蝶の様な完全変態をする昆虫とは、その点異なる。 セミが地上に出てくるのは、交配と産卵をするためで、地上での命は概ね数週間である。セミは地中で幼虫の姿で人生(ではない)「蝉生」の大半の時間を過ごしているのだ。 日本で普通に見かけるアブラゼミは、地中での生活は6年ほどだそうだ。春になって真っ先に鳴き始めるニイニイゼミは、前年産卵されたものが一年後に羽化しているのだそうだ。「蝉生」も様々である。 アブラゼミなどは毎年出てくるが、蝉の仲間にはある周期でしか地上に現れてこない種類もあって、これを周期ゼミという。この周期ゼミの仲間に、素数ゼミというのがいる。北アメリカで見られるセミだ。 北アメリカの素数ゼミは、13年ごとに大発生するものと、17年ごとに大発生するものと2種類ある。大発生すると書いたが、このセミには中発生も小発生も無い。つまり、他の年には全く世間に姿を見せない。この発生周期が共に素数だから素数ゼミと呼ばれるのだ。 この素数ゼミ、2004年にニューヨーク州で発生したときには、その数約60億匹に及んだというから凄い。佃煮しても処理できないほどの数のセミが、街路樹や家の壁を埋め尽くし、地面は羽化しようと地上に出てきた幼虫の大群で埋め尽くされ、歩くことはおろか、車のタイヤもスリップするほどだったそうだ。 こんなに沢山のセミでは、流石の芭蕉先生も、余りのうるささに静けさなど感じるどころではなかったろう。 さて、素数とは自分自身と「1」でしか割り切れない正の整数のことだ。 セミが素数などと言う概念を知っているはずはないから、こういう発生周期を持つセミが生まれてきたのには、何か自然の理由があったはずだ。 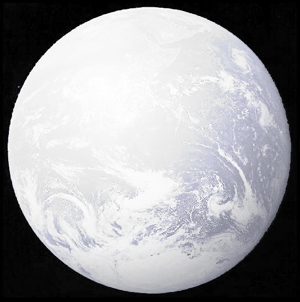 静岡大学の吉岡仁教授(数理生態学)によれば、こういうことらしい。(それにしても数理生態学などという学問分野があるんだなぁ。) 静岡大学の吉岡仁教授(数理生態学)によれば、こういうことらしい。(それにしても数理生態学などという学問分野があるんだなぁ。)ずっと昔地球が、全球凍結するほどの非常に寒冷な環境にあったとき、セミの幼虫が地下で充分に成長するには10年以上の時間を必要とした。(又、吉岡先生によれば地下に居る時間が19年以上だと長すぎたのだそうだ。) それでも栄養不足は深刻で、充分に成長することが出来て地上に出てきても、地上の環境も悪く、成虫として交尾することができる個体数は容易に増えなかった。つまりこのセミの種としては存亡の危険があった。そこで、交尾期、つまり成虫になる時期の足並みを揃えることで、交尾チャンスを増大させ、より多くの子孫を残せる方向に進化の圧力がかかった。 又セミは成虫になってしまうと他の動物の恰好の捕食対象になる。だから交配のチャンスを増やすようにするためには、食べられてしまう確率を織り込んで、なるべく多数の子孫を一度に残す必要がある。捕食する側の、主に鳥類の生活周期は3~5年だから、こういう周期と重ならなくて、且つ捕食習慣が捕食者側に定着しにくいほど長い発生周期である方が望ましい。そうなると発生周期は素数であるほうが良い。素数は1以外の他の数と公約数を持たないからである。 こうなると、セミの幼虫が過不足なく成長できて、相対的に安全な発生周期は10年以上19年未満で、11年、13年、17年の何れかの素数周期となる。 更には同じセミ同士でも、折角収斂した発生周期が交雑によって乱れてしまうと、12年ゼミや15年ゼミ、16年ゼミなどと分散してしまって、期待できるはずの大量発生が難しい。そうなることを防ぐためには、セミ同士でも、お互いに発生周期が重ならないほうが良い。 因みに、「11年ゼミ」と「13年ゼミ」では143年毎、「11年ゼミ」と「17年ゼミ」では187年毎に、発生周期が重なる。「13年ゼミ」と「17年ゼミ」では、これが221年毎となり、一番長い。 こういった事が長ぁ~い時間をかけて「進化圧力」として働き、最終的に13年ゼミと17年ゼミが現代まで生き残ったのだそうだ。 素数ゼミは厳しい環境下で、大群という「数の力」をもってして、種の生き残りを図ったのだ。 ところで、先日このブログでホシムクドリの大群について書いた。 この鳥は多い時には数十万羽にも及ぶ大きな群れをつくり、それが空を飛ぶさまはまるで巨大なアメーバのように見える。時に黒く凝集し、或いは突然それが解け、又再びアメーバの触手が伸び・・・と、見ていると誰かに操られているか、又は巨大な集団意志が存在しているような気がしてくる。 しかし、それは一羽のムクドリに組み込まれた単純なルール、つまりローカルルールが作用しているだけだと書いた。 イワシやニシンの群れの集団遊弋行動もこの比較的単純なローカルルールの作用によるものだと。 しかしムクドリやイワシがこういうルールを体得したのにも、何か「進化上の圧力」が働いた結果であるはずである。 群れで暮らす生き物には「希釈効果」というものが働くそうだ。 先ず、:単独生活では捕食者と出会った時に生き延びる確率が低くても、群れになれば自分が狙われる確率は減る。つまり、我が個体が殺される危険は希釈される。 そして、群れの中に子供や病気などで運動能力の劣った個体がいて、それらが捕食されれば自分は助かる確率がより増える。このように常に群れを作り自分が捕食される可能性を低く「薄め」ようとすることを「希釈効果」というのだ。 捕食者は捕食対象が緊密に群れている時には攻撃しない傾向がある。これは、如何に強力な捕食者でも、群れは全体として大きな塊として見えてしまい、それ自体に捕食者は大きな威圧感を覚えてしまうからだろう。我われが、イワシやムクドリの大群を見て、何となく巨大な集団意志を感じ、時に恐ろしさや気味悪さを感じるのと同様の現象が、捕食者にももっと原初的な形で感じられるのだろう。 だから捕食者は群れの周辺を威嚇しながら、そこから脱落する個体を狙う。 例えば、ムクドリの群れはハヤブサに追いかけられたとき激しく飛び回る。ハヤブサはその内群れからはぐれてしまった個体を狙う。群れからはぐれ、個体になってしまえば、それは美味しい餌にしか過ぎない。  これは一見すると、群れが協調してハヤブサから逃れようとしているように見えるが、そうではない。そんな集団意識など無いのだ。ハヤブサは群れ全体を相手にはしないが、途中で諦めて群れから離れることはまず無い。その内群れの中のどれかが、タイミングを間違えるか疲れるかして、群れを離れる時期が必ずやって来る。ハヤブサはそのはぐれものをすかさず狙い、捕食するのだ。 これは一見すると、群れが協調してハヤブサから逃れようとしているように見えるが、そうではない。そんな集団意識など無いのだ。ハヤブサは群れ全体を相手にはしないが、途中で諦めて群れから離れることはまず無い。その内群れの中のどれかが、タイミングを間違えるか疲れるかして、群れを離れる時期が必ずやって来る。ハヤブサはそのはぐれものをすかさず狙い、捕食するのだ。つまりムクドリの行動は、実は群れを守ろうとしているのではなく、群れから早く脱落者を出すことによって個々のムクドリが長時間飛び回らなくても済むような状況に持ち込むために、希釈効果を積極的に利用していると考えられるのだ。 結局、群れ行動を確実に取ることが出来る個体が生き残りやすくなる。群れから外れた個体は捕食されてしまい、従って遺伝子を残せないので、全体としてはどんどん緊密な群れを作る能力を高めることになる。 これはイワシでもニシンでも、或いは他の群れを作る生き物でも同様だろう。 素数ゼミも、集団からの跳ね上がりものを排除していく過程を積み重ねて、現在のような習性を獲得するようになったと考えられる。 群れとは、個体に対してそういう冷淡な面も持っているのである。 ところでこの素数ゼミ、北米では低脂肪・高タンパクの健康食だそうだ。何しろ13年か17年に一度しかお目にかかれないレアものだ。珍味として、食用に供されているらしい。 それにしても60億匹のセミだ。どう料理して食べるのか知らないが、何となく食欲は沸いてこない。でも我々だってイナゴを佃煮にして食べる(私は信州のイナゴの佃煮は好物だ)から、これは単なる食べず嫌いなのかもしれない。 今度ニューヨーク州に17年ゼミが大発生するのは2022年の予定だ。その頃アメリカに行ってセミ料理に挑戦してみるかどうか、・・・・まだ決めていない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010.08.16 19:49:57
コメント(0) | コメントを書く
[そこいらの自然] カテゴリの最新記事
|