
|
|
|
カテゴリ:Movie(エットレ・スコラ)
『マストロヤンニ自伝』(小学館、押場靖志訳)で、マストロヤンニがわざわざ1章を割いて解説し、「本当に見事」「映画のお手本」「傑作とはこういう映画のこと」と言っている作品がある。マストロヤンニ主演映画の中では案外地味な『特別な一日』がそれだ。
マストロヤンニが重要な場面として挙げたのは、これまた作品の中でもかなりさりげない「電話のシーン」。ここについてマストロヤンニが何を語ったか聞いてみよう。 「私の役はホモセクシャルで、明らかに自分の彼氏と話しているのです」「私は彼(=監督のエットレ・スコラ)に言いました。『ぼくにだって多少の慎みがあるから言うのだけどね、このシーンは全部背中から撮ったらよいと思うんだ。うなじの後ろからカメラで近づいてくれないかな。ぼくの台詞があまりに刺激的になっても困るだろ。お客さんに不快な思いをさせるわけにはゆかないからね』。スコラは納得してくれました。その結果このシーンは、映画の中でも特に素晴らしい場面の1つになったのです」(『マストロヤンニ自伝』) このマストロヤンニの発言には、かなり虚をつかれた。『特別な一日』は過去に見ていたが、マストロヤンニ演じるガブリエレがソフィア・ローレン演じる人妻アントニエッタに出会い、その日のうちに密かに関係をもつというストーリーで、ガブリエレは反ファシストだった記憶はあったが、ホモセクシャルだったという印象がほとんどなかったからだ。 そこでさっそく再観賞してみた。マストロヤンニの自伝を読まなければ、2度見てもわからなかったかもしれない――これは確かに、ファシスト政権による性的マイノリティ弾圧のさまを描いた映画だった。  重要な「性的マイノリティ」という概念を見落としてしまったのは、1つにはイタリアの事情、つまりファスシト政権のもとで、同性愛者がサルデーニャに島流しになっていたという事実を日本人ゆえに知らなかったせいもある。イタリア人ならある程度わかっていることだから、ことさら説明的に描写する必要はないのだろう。だが、こちらにはピンとこないので、映画のタイトルの『特別な一日』というのが、ガブリエレにとっては、島流しになる前の最後の一日だったのだということを最初に観たときは見逃してしまっていた。 『特別な一日』には歴史的な意味もある。映画冒頭で語られるイタリアにとっての特別な一日。それは、ヒットラー総統がムッソリーニ政権下のイタリアを訪問するということだ。 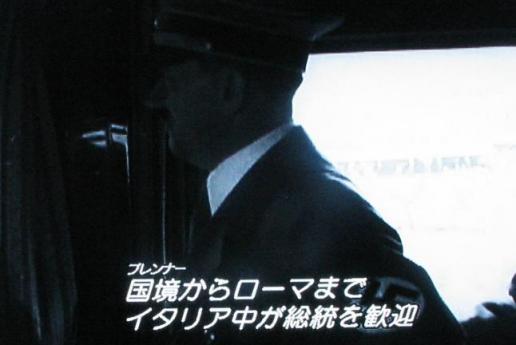 この――当時のイタリアの一般人にとって――特別におめでたい日を祝おうと、市民がこぞって出かけていく。 アントニエッタの家族も全員外出する。1人残り、家事に追われるアントニエッタ。  髪は乱れ、化粧っけもない。生活に疲れた主婦そのもののアントニエッタ。 だがこの日彼女は、ガブリエレに出会い、特別な関係をもつ。彼女にとっては、長らく忘れていた女性としての自分を取り戻す一日になる――それがアントニエッタにとっての「特別な一日」。彼女はガブリエレが島流しになることを知らない。また会えると思っている。彼が「自分は男色家」と言っても、その本当の意味、その運命を最後まで理解していない。彼女はファシスト政権についても、それが悪だとか、間違いだとかは思っていない。時の権力の頂点に立つ男にたまたま会ったときの感激を、ガブリエレに素直に語ったりしている。長いものに巻かれている当時の普通のイタリア人女性なのだ。  彼女の誤解が、そのままMizumizuの誤解になってしまった。マストロヤンニと同性愛者というイメージがあまりにかけ離れていることもある。また、その描き方が非常に「慎み」深かったせいもある。ガブリエレの「彼氏」もまったく出てこないし、彼がアントニエッタに向かって「自分は同性愛者だ」と叫ぶシーンも、単に、「感情的になって、露悪的なことをオーバーに言っている」ように見えたのだ。  だが、そうではなかった。よくよく観ると、映画の冒頭ガブリエレは自殺をしようとしていた。迷っているところに、アントニエッタがたまたま訪ねてきたので、救われたのだ。それをガブリエレは電話で「彼氏」にさりげなく話している。しかも、その「愚行」はその日が初めてではない。何度か自殺を考えたことがあるのだ。 そう、彼は絶望し、追い詰められている。明日島流しになるからだ。だが、その事実を電話の向こうの彼氏には黙っている。彼を守るためだ。だが、もう明日になったら2人は話すこともままならない。だから、ガブリエレは思わず、彼氏に「何かしゃべってくれよ! 何でもいいから! 今日はぼくの特別な一日なんだ」と言っている。今日が最後だと告げられぬまま、(恐らくは「会おうか」と電話の向こうで申し出ている彼氏に)「今2人で会うのは危険だ」と押しとどめ、「(逮捕されても)すぐ釈放になるから」と安心させている。 「映画の中でも特に素晴らしい場面の1つ」とマストロヤンニが自伝で述べた電話のシーン。  同性愛は悪。ファシスト政権下で差別と弾圧の対象にされた性的マイノリティ。  会おうとする「彼氏」を制止するガブリエレ。最初に見たときは、反ファシストの同志との会話だと勝手に思い込んでいた。  次第に昂ぶってくるガブリエレ。「このシーンは背中から撮って」とマストロヤンニがリクエストした。  確かに、これは「同志」への問いかけではない。マストロヤンニが言うように「彼氏」との会話なのだ。  この言葉は今のガブリエレの心情でもあるが、明日からサルデーニャでガブリエレが想うことでもある。  入ってきたアントニエッタに電話の会話を聞かれて、慌てて取り繕うガブリエレ。 だが、すぐ釈放されないことはガブリエレはよく知っているのだ。それはアントニエッタに語った「島流しになった友人の話」からわかる。 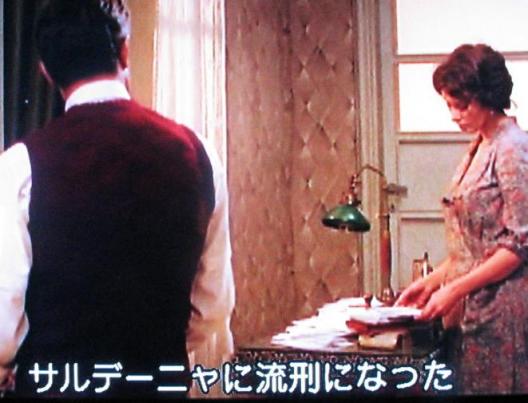 「チビタベッキアの港に友人を見送りに行った。彼は戻ってこない」と話している。それは明日の彼の運命なのだ、アントニエッタが知らないだけで。 アントニエッタが知らない彼の運命を、観客は最後の最後にガブリエレを迎えに来た男たちとの会話で知ることになる。これもとてもさりげないフレーズだ。ガブリエレは、男たちに「出航はいつ?」と聞いている。  やはり彼は、これからサルデーニャに流されるのだ。壁にかけた絵を取り外し――それはおそらく、彼氏であるマルコとの思い出の品なのだろう――包んで抱え、男たちに連れられて出て行くガブリエレの姿を、アントニエッタは自宅の窓から見かける。観客には、もうこの2人がこれっきりであることはわかっている。だが、アントニエッタは最後まで知らずにいる。彼女が真実を知るのはいつだろう? 2人が結ばれたあと、「また来週会える?」と彼女は聞いた。  ガブリエレは何も答えなかった。彼女からガブリエレの表情は見えない。だが、観客には見えていた。それは硬直した、表情のない表情だった。彼女はガブリエレの沈黙を暗黙の了解と受け止めたのだろう。だが、来週、彼はもうアントニエッタの手の届く場所にはいない。 彼は、たとえ女性と「できた」としても、自分が同性愛者だということは変わらないと言う。  だがこうも言っている。「特別な一日に、女性とこうした素晴らしい経験をもった。それがぼくにとっては重要なんだ」。 彼のセクシャリティをより細かく、正確に記述するなら、「男性の肉体をもちながら、性愛の対象として男性を指向する単性愛者」ということになるだろう。彼はそうした自分から逃れたいと思ったこともあるはずだ。アントニエッタにことさら近づいたのも、そうした願望の表われともとれる。「世間一般の男性」と同じになってみたい――あるいは少なくとも、そのフリだけはしてみたい。だが、同性を指向する単性愛者であるというのは彼の宿命であり、自分で変えることはできないのだ。 屋上の物干し場で2人が肉体的に接近するシーンは、表向きは男女の情事を予感させる場面だが、結末を知ったとき、自分から逃れたい男と日常から逃れたい女の願望は、実際には決して1つに溶け合うことはないという哀しさを秘めていたことに気づかされる。 この特殊な男性を表現するために、確かにマストロヤンニは細かい「工夫」をしている。たとえば指にはめた大きな指輪。ヘンにオシャレだ。それに、アントニエッタと踊るときのガブリエレの腰つき。微妙にクネっている。どれもわざとらしくならない程度に、微妙に「それ風の感じ」を出している。 彼女は出会ったばかりのガブリエレが、わざわざ彼女の家に本をもってきてくれたとき、「自分に気がある?」と誤解した。観客もこのときはそう思ったはずだ。だが、最後になってわかるのだ。あれは「明日はここからいなくなる運命の人間」が、近所の感じのよい奥さんに、自分がいなくなっても自分を思い出してくれればと思ってやった、下心とはまったく無縁の切ない行為だったのだと。 自分とあまりにかけ離れた世界のことはアントニエッタには理解できない。最後まで誤解したまま、だが、女性としての喜びや自信を見出した彼女の姿もまた切なく、美しい。 ある特殊な世間のムードの中で、いかに少数派がさげすまれ、虐げられるか――ファシズム批判でありながら、また、まったく違った精神世界に住む男女の出会いとつかの間の情事をとおして、彼と彼女が垣間見た儚くも切ない夢を日常的な情景の中に描き出した、確かに傑作中の傑作。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008.09.26 04:33:28
|