
|
|
|
カテゴリ:Movie (ベルナルド・ベルトルッチ)
『スターリングラード』でも好演したジョセフ・ファインズが、最初にスクリーンデビューしたのがベルナルド・ベルトルッチ監督の『魅せられて(STEALING BEAUTY)』だった。
偶然にもジャン・マレーにとっては、これが最後の映画出演になった。ジャン・マレー自身が 『魅せられて(STEALING BEAUTY)』を最後の映画と思い決めて出演したのかどうか、明確にはわからないのだが、実はこの作品、監督のベルトルッチはマレー、そしてジャン・コクトーに最大限の敬意を密かに捧げている。 ジャン・マレーに対する敬意は、衣装でもわかる。『魅せられて(STEALING BEAUTY)』のクライマックスシーンでもある、神秘的で淫靡な雰囲気に満ちたパーティシーンで、ベルトルッチは主役のリヴ・タイラーとチョイ役のジャン・マレーだけに、当代きってのイタリア人デザイナー、ジョルジオ・アルマーニの衣装を着せている。 また、ジャン・マレーの自伝から取ったエピソードを、さりげなくシナリオに入れている。 たとえば、コレ↓ 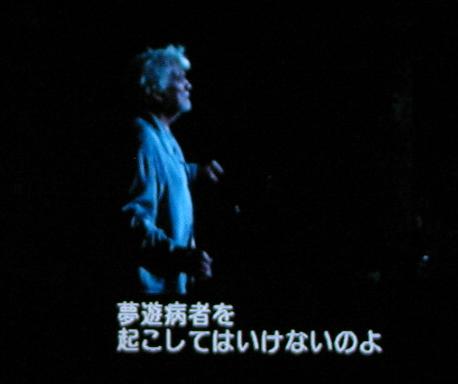 有名な画商であるギヨーム氏(マレー)が、夜、夢遊病者となって庭をさまよい歩いている。それを見た若者たちが言う台詞、「夢遊病者の人は起こしてはいけない」――これは、マレーがちょうど『悲恋(永劫回帰)』でスターになったころ、コニャックを飲みすぎて起こしたエピソードから来ている。 飲みすぎたマレーは、翌朝起きると、自分の部屋の窓がすっかり開いているのを見て驚く。寝る前は確かに閉まっていたはずなのに。さらに友人から思いもかけない話を聞く。夜の間に、マレーが友人とそのフィアンセの部屋に入り込み、窓を全部開けて出て行ったのだという。もちろんマレーには何の記憶もなかった。別の友人がマレーの友人のフィアンセの女性に、 「もしジャノがキミのベッドに入り込んだら、どうするつもりだった?」 と聞いたところ、 「夢遊病の人は、決して起こしてはいけないって、よく聞かされていたわ」 と答えたという(『ジャン・マレー自伝 美しき野獣』石沢秀二訳 新潮社より)。 『魅せられて』は、19歳のアメリカ人・ルーシー(リヴ・タイラー)が、詩人だった母親の自殺をきっかけに、育ててくれた父親が自分の本当の父ではないことを知って、父を捜しにイタリアに来るという話だが、これはタイラー自身にとって実話に近い話であると同時に、ジャン・マレーにとっても実話に近い。 マレーは幼いころに母と別れた父に長年会いたいと思ってきた。ところが会おうとすると母親が邪魔をする。結局父の死の直前、わずか1週間前にとうとう対面が実現するのだが、父の死後、実の父親は別人だと知らされるのだ(これについては2008年8月12日からのエントリー参照のこと)。 また、ルーシーに思いを寄せる、白血病で余命いくばくもないアレックス(ジェレミー・アイアイズ)の台詞は、完全にコクトー語。  「星」というのは、コクトーがマレーにさかんに言っていた言葉だ。ただし、コクトーにとってマレーが「星」だということではない。「ぼくたちの星が守ってくれる」「君の星を信じている」という具合に、幸運の守り神のような象徴的存在がコクトーにとっての「星」だった。  病気が進行し、衰弱してきたアレックスがルーシーに言う台詞も、晩年、病気と縁が切れなくなったコクトーがさかんにマレーに書き送っていた言葉と同じ。 しかし、『魅せられて』でのジェレミー・アイアンズの臨場感あふれる演技は、ほとんど戦慄的とも言っていい。本当に、もうすぐ死んでしまいそうな人に見える。病のもつ負の側面、人を畏怖させるある種の「穢れ」のようなものまで、そのたたずまいに出している。まもなく消えようとする自分の命の灯火。だからこそ強くなる、若く美しく、これから自分の人生に踏み出そうとしているルーシーへの憧れと執着。 コクトー語に話を戻すと、このフランスの詩人にとって、俳優ジャン・マレーは、天使だった。このキーワードもちゃんとシナリオに入っている。  コクトーはマレーへの手紙でも生涯、「ぼくの美しい天使」「ぼくの善良な天使」と呼びかけている。 マレーのほうは、最初のころこそ、「ぼくは天使なんて、そんな崇高な人間じゃない」と何度もコクトーに「わからせようとした」らしいが、途中であきらめたようだ(笑)。 コクトーも詩人なら、ベルトルッチも詩人、そしてルーシーも詩人なのだ。  詩を書くルーシー。単語が水面に浮いてくる泡のように、画面のあちこちに現れては流れ、消えていく。「詩」を書く人の頭の中の様子を、「詩的」に映像化したかわいらしい場面。 また、ルーシーがこんな風につぶやく場面  では、通りかかったギヨーム氏(中央)が振り返り、「愛というものはない。愛の証しだけがある」とフランス語で言って去っていく。これはもちろん、ジャン・コクトーの言葉だ。 俳優ジャン・マレーを微妙におちょくっているような場面もある。小さな女の子に、「ギヨームさんって、とってもおおげさなの」と、マレーの演劇スタイルをユーモアをこめて風刺するような台詞を言わせたり、マレー好みの痩身・黒髪の若い青年を出して、ギヨーム氏に向かって、わざわざフランス語で、「一緒に帰りませんか?」と言わせるシーンまで入れたりしている。  軍服姿だというのが、またツボなこと。 もちろん、快く申し出を受けるギヨーム氏。同席していた若者が、察したようにコッソリ苦笑いしている。こういうギャグ、晩年のマレーは監督と一緒になって、どうもわざとやっているようでもある。 しかし… 完全に楽屋落ち… ジャン・マレーのことを知らない観客には、何がなんだかわからない台詞と進行じゃないだろうか。 パーティのシーンで、杖をつき、女性に支えながら歩いてくる老紳士ギヨームの姿は、明らかに「オルフェの遺言」(コクトー監督)でマレーが演じた「アンティゴネーに導かれる盲目のオイディプス」のイメージの再現だ。 この作品、マレーはあくまでチョイ役(特別出演というべきか)なので、いなくてもいいといえばいいのだが、トスカーナの芸術家共同体に集うメンバーの1人として、それなりに不思議な存在感を出している。 基本的にはルーシーの初体験を描いた青春ドラマなのだが、老いた人、病気の人、若さを失いつつある人、精神的に問題を抱えた人… とさまざまな年代、さまざまな性格のキャラクターを出すことで、彼らがそれぞれ違う色のモザイク石となって、「交錯する人生」という1つのモザイク画を完成させる。 そして、美しいトスカーナの風景と…  それに溶け込むリヴ・タイラーの輝くばかりのみずみずしさ。すんなりと長い健康的な脚線美が目を奪う。  こうした美しさは、数年、いやひょっとしたら数ヶ月で消えてしまう、儚いものなので、タイラーがこの年齢で、この作品に出たというだけでも、十分に価値がある。 ベルトルッチという人、ウィキペディアには、「イタリア人ではあるが監督デビュー前からロベルト・ロッセリーニとピエル・パオロ・パゾリーニ以外のイタリア人監督を認めないと公言しており」と傲慢な人柄を感じさせるエピソードが紹介されているが、必ずしもそうではないように思う。 たとえば、『ラストタンゴ・イン・パリ』では、主人公(マーロン・ブランド)が妻に浮気をされていた話が出てくるが、その浮気相手というのが…  マッシモ・ジロッティ。 ルキーノ・ヴィスコンティ監督の『郵便配達は2度ベルを鳴らす』で主人公、つまりヒロインの人妻の浮気相手を演じた俳優だ。 上は『ラストタンゴ・イン・パリ』でのジロッティ初登場シーンだが、これは『郵便配達は2度ベルを鳴らす』での、ジロッティの初登場シーン↓  にあまりにもソックリ。首の傾げ方が右か左かだけで、角度まで似ている。 おかげで、ジロッティがこんなに年を取っているにもかかわらず、『ラストタンゴ・イン・パリ』を観たとき、すぐにジロッティだとわかった。 『郵便配達は2度ベルを鳴らす』でジロッティの演じた主人公は、若さの情熱にまかせて、浮気相手の女性の夫を殺害するのだが、『ラストタンゴ・イン・パリ』では、浮気をした女性が自殺してしまい、夫(マーロン・ブランド)と浮気相手の男性(ジロッティ)とが、彼女に買ってもらった同じ柄のガウン(というか、同じものを2つ買て、あっちとこっちに渡しただけ?)を着て、  しんみりしているという、泣くに泣けない、哀愁だだようシーンが… この役にあえてジロッティを使い、あんなにもそっくりな初登場シーンを30年もたって再現したのは、ベルトルッチがヴィスコンティ作品に敬意を払っている証拠だと思う。 『魅せられて』で、ジャン・マレーに出演を要請し、マレーの自伝から取ったエピソードを挿入したり、コクトー語を散りばめたりしたことも、コクトー&マレーという偉大な先輩表現者への尊敬の念からだと思うのだ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009.05.20 02:01:25
|