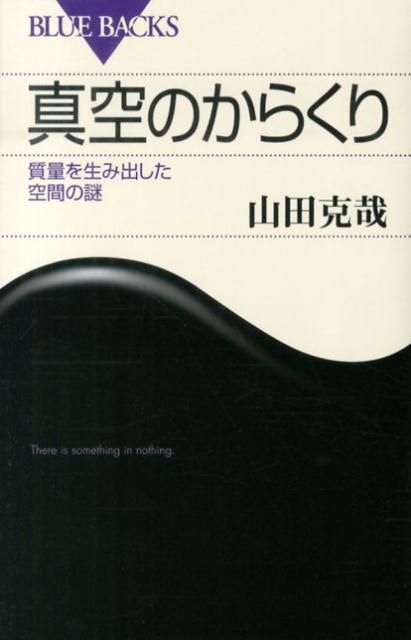 |  実に奇妙な話ではありますが、現在までのところ量子力学に違反する物理現象が一つも観測されていないことが、「真空のエネルギー」の存在を強固に下支えしています。(47ページ) 実に奇妙な話ではありますが、現在までのところ量子力学に違反する物理現象が一つも観測されていないことが、「真空のエネルギー」の存在を強固に下支えしています。(47ページ) |
| 著者・編者 | 山田 克哉=著 |
|---|
| 出版情報 | 講談社 |
|---|
| 出版年月 | 2013年10月発行 |
|---|
同じブルーバックスで『光と電気のからくり』『量子力学のからくり』『時空のからくり』『E=mc2のからくり』『重力のからくり』を著した山田克哉さんの著書。アメリカで教鞭をふるい、アメリカ物理学会会員でもある。
『重力のからくり』の後に読んだのだが、こちらの内容の方が専門的と感じた。とくに第6章が難解で、必要な数式は、例によって山田さんの絶妙な解説で理解したつもりなのだが、量子力学の不思議な性質(概念?)を理解するには未だ時間がかかりそうだ。少なくとも、ヒッグス場の誕生の瞬間とその役割はわかってきた。
第1章では、何も無い真空に無限のエネルギーがあることを紹介する。
量子力学により、粒子の完全静止は不可能であることが明らかになった(11ページ)。アインシュタインとオットシュテルンは1913年、金属箱の温度が絶対ゼロ度になっても、箱の中には振動数 \( v \) で振動している電磁波が残っていることを明らかにし、そのエネルギー(ゼロ点エネルギー)は \( \frac{hv}{2} \)であるとした(36ページ)。そして、1997年、アメリカのスティーブ・ラモローがカシミール効果を計測し、真空にエネルギーがあることを実証した。
一方、アインシュタインは、光を波ではなく粒子として扱うことによって光電効果を見事に説明し、その功績で1921年のノーベル物理学賞を受賞した(40ページ)。ここで、光子1個のもつエネルギーは \( E = hv \) だが、ゼロ点エネルギーはその半分だ。光子はそれ以上分割できないはず。これはどういうことだろうか?
第2章から3章にかけて、何も無い真空からエネルギーを叩き出せることを紹介する。
ド・ブローイは、電磁波が質量のない光子という粒子として振る舞うなら、質量のある電子も波として振る舞うことを示し、両社の関係を \( 波動性 \approx \frac{プランク定数 h}{粒子性} \) という式で表した。
ここで登場するプランク定数 \( h \) は(6.62607015 \times 10^{-34}m^2 kg/s \) という極めて小さい定数なのだが、なぜこれほど小さな値でなければならないのかは分かっていない。だが、これほど小さいがゆえに、原子が形作られ、また、目に見える大きさの物体は波として振る舞うことがないという結果をもたらした。
ドイツのヴェルナー・ハイゼンベルクは1925年に量子力学を築き上げ、翌1926年にオーストリアのエルヴィン・シュレーディンガーが波動力学を提唱するが、やがて両者は同じ理論であることが分かり、そこから不確定原理が導き出された。不確定性原理によれば、量子は位置と運動量を同時に確定させることはできず、エネルギーと時間間隔を同時に確定することもできないという不思議な結論が導き出される。つまり、不確定性原理が許す範囲内でエネルギー保存則は破られる(65ページ)。ここに真空のエネルギーの秘密が隠されている。そして、その不確実さを示す式にもプランクの定数\( h \)が登場する。
真空から粒子を叩き出すための実験装置を「コライダー(衝突型粒子加速装置)」と呼ぶ。コライダーを使って陽子と陽電子を光速に近い速度にまで加速し衝突させると、そこに瞬間的に静止した1個の仮想光子が現れ、真空を揺さぶり、消えてゆく。
その後、カシミール効果やラム・シフトの観測を通して、真空のエネルギーが実在することが明らかにされた。
第4章では、力が真空を伝わる仕組みとしてのゲージ場を説明する。
自然の力には、力の強さの順に、1)強い力、2)電磁力、3)弱い力、4)重力の4つが存在(120ページ)するが、いずれの粒子間の相互作用もゲージ粒子の交換によって発生する。そしてゲージ粒子は質量が仮想粒子で、相互作用する2つの素粒子から瞬時に創生または吸収・消滅する様子が、あたかも交換されるように見える(133ページ)
。このゲージ粒子が真空を攪乱する張本人(147ページ)であり、現実の現象を起こしているため、仮想だからといって無視することができない。たとえば、精密測定によって実測された電子磁石の強さは、完全無欠と考えられていたディラック方程式の結果より0.1%大きい。これが、周囲の真空が電子に影響与えているためで、仮想粒子は観測ができないから、計算によって求めるしかない。
第5章では、弱い力と質量の起源をめぐる謎を解き明かしていく。
ゲージ粒子が質量をもつと対称性が破れてしまう(178ページ)。この世のすべての素粒子は、フェルミ粒子かボース粒子のいずれかに属しており、スピン角運動量が整数かどうかで区別される。ゲージ粒子は全てスピン1のボース粒子。陽子や中性子、電子やクォークなど、原子の構成要素となっている素粒子はことごとくフェルミ粒子だ(189ページ)。
世に存在する物質がすべてフェルミ粒子だけからでき上がっているのは、パウリの排他律によるものだ。原子を構成するフェルミ粒子が同一の物理状態をとれないために、原子は決して潰れることがない。一方、ボース粒子にはパウリの排他律は適用されず、同じ種類のボース粒子がたくさん集まると、それらすべてのボース粒子が同時にまったく同じ物理状態(同じエネルギー、同じスピン、同じ位置など)になることが許される(191ページ)。
現在の素粒子理論である「標準模型」では、下図のように6種類のクォークと6種類のレプトンを扱う(200ページ)。
なぜ現在の宇宙に反粒子がないのかというと、粒子とその反粒子を比べた場合、弱い相互作用の生じ方に違いがあることが予測されている(203ページ)。弱い力を媒介するWボゾン(仮想粒子)の質量は、クォークやレプトンの質量よりもはるかに大きく(つまり、エネルギーが大きい)、不確定原理に従って存在できる時間間隔は極端に小さく、弱い力の到達距離は原子核の直径の1000分の1程度にとどまる。そして、弱い相互作用は、理由は分からないが、「左巻き」のフェルミ粒子だけを選り好みする(209ページ)。
第6章では、質量を生みだしたヒッグス粒子について解説する。
誕生直後の宇宙は完全対称性を保っており、4つの力は1つだったと考えられている。ところが、真空の相転移が起き、その完全対称性が自発的に破れた。このときヒッグス場が誕生し、弱い力を運ぶ3つのゲージ粒子は質量を獲得する。これを「ヒッグス機構」という(254ページ)。なお、真空の相転移によって発生したのはヒッグス場のみで、他の3つの場はこれと直接関係しない(251ページ)。
真空に相転移が起こったあとも光子だけは質量を得ないままで、光子が媒介する電弱相互作用は電磁相互作用と弱い相互作用に分かれてしまう(258ページ)。
しかし、実測された素粒子の質量とヒッグス場の導入によって理論的に得られた質量との一致を見たのは、弱い力を運ぶ3種のゲージ粒子だけで、他の粒子の質量は未だ説明されていない(271ページ)。
そもそも、現在の宇宙はエネルギーが最も低い状態なのか。将来、再び真空の相転移が起こる可能性はないのか――宇宙には、まだまだ分からないことが多い。
今後、真空の相転移が起きるかどうかは誰にも分からないのだが、もし起きたら世界が破壊されるという話はSFネタになっている。たとえばアニメ『宇宙戦艦ヤマト』における波動エネルギーが、それだ。本書ではコライダー(衝突型粒子加速装置)がその引き金となる噂に触れ、世界の各地で「コライダー建設反対運動」が起こっていることを紹介している。
超伝導におけるマイスナー効果は、何度か実験を見たのだが、光子が質量を得た結果起きる量子力学現象ということが分かったのは収穫だった。
2019年にキログラムの定義が、実体(原器)から物理定数に変更になった。質量については、まだまだ分からないことが多いようだ。真空は何も無い空間ではなく、分からないことだらけの空間である。

