村上春樹「ノルウェイの森( 上・下)」(講談社文庫)
 およそ10年前、ぼくは高校生に向かって、こんなふうに「村上春樹」を語っていました。今でも、同じように感じているところがほとんどだが、少し考えが広がったところもあります。それを語り始めると、少々手間がかかりそうです。とりあえず、ぼくの2010年の「ノルウェイの森」をお読みいただければ嬉しいのですが。
およそ10年前、ぼくは高校生に向かって、こんなふうに「村上春樹」を語っていました。今でも、同じように感じているところがほとんどだが、少し考えが広がったところもあります。それを語り始めると、少々手間がかかりそうです。とりあえず、ぼくの2010年の「ノルウェイの森」をお読みいただければ嬉しいのですが。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 中間テストに突入する。テスト初日の午後には保護者会がある。「ああ、テストの問題は!?」「ああ、保護者の人に、何しゃべろ!?」と行き詰って、ほとんど寝ないまま、突入!ということになってしまったのだが、実はおバカな理由がある。村上春樹「ノルウエイの森(上・下)」(講談社文庫)にハマっていたのだ。
発端は、
「ノルウエイの森が映画になっとうで。」
と、我が家で話題になってしまったことにある。
「どんな話やのん。」
「いや、そんなこと。読む前に言うたら、おもろないやろ。エエーっト、直子いうねん。主人公の、彼女は。それで、主人公はワタナベ君。神戸の子やで、二人とも。」
「菊地凛子や、それが。主人公は松山ケンイチ。」
という訳で、あったはずの本を探し始めたのだがこれが見当たらない。とうとう、
「ブック・オフで探してきてよ。」
と、主客転倒。
「あったよ、合計210円。」
「はいはい。」
と、なぜか、買ってきたぼくが、先に読み始めて、ハマってしまったのだ。
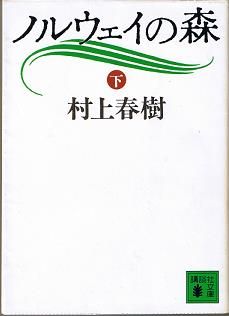 村上春樹の小説はもう馴染みだし、この小説だって1980年代の終わりに大ブレイクした時に単行本で読んだ。今さらハマルとは思わなかった。
村上春樹の小説はもう馴染みだし、この小説だって1980年代の終わりに大ブレイクした時に単行本で読んだ。今さらハマルとは思わなかった。
もしも、高校生の皆さんの中に、彼のファンがいらっしゃれば、きっと同感されると思うけれど、彼の文体には、不思議なドライヴ感があることは確かで、読み始めると止められないところがある。しかし、なぜ、今、ハマってしまったのか。
大ブレイクした時に購入したのは、真っ赤な上巻と深い緑色の下巻のセットがおしゃれな本だった。本がおしゃれの小道具になる時代だった。最近、復刊されている文庫本はその装丁を復活して本屋さんに並んでいる。

 もっとも、僕には、当時、その本を人前で開くのが恥ずかしかった記憶がある。
もっとも、僕には、当時、その本を人前で開くのが恥ずかしかった記憶がある。
「どうも、時代についていけてないな。」
僕はそんなふうに思った。だからだろうか、今回読み直しながら、この小説があの時、なぜ、あんなに評判になったのだろうと、とても気になった。
主人公の「ワタナベくん」は神戸から東京に出てきた大学生。彼の高校時代の親友の恋人だった「直子」がヒロイン。二人にとって、それぞれ親友であり、恋人だった「キズキくん」は二人を残して自殺しているという設定なのだが、東京で再会した二人は物語の必然のように恋に落ちる。しかし、この恋は成就しない。ストーリーとしてはそれだけの話。
ところで、恋が成就するとはどうなることをいうのだろう。ただ、おしゃべりしたり、手を握り合っているだけじゃなくて、セックスして、やがて、めでたく結婚して、子供が出来て・・・ということだろうか。互いに、肉体だけでなく心の全てをさらけ出して、求め合うことができる事を言うのだろうか。それならば、この二人はかなりな所までたどり着いているといえるのだが、あと数センチ、いや数ミリかな、届かない所で終わってしまう。
小説を読めば、このたとえが単純な比喩でないことはわかると思うのだが、ともかくも、これだけ深く愛し合いながら破綻せざるを得ないように描かれる二人の関係が、リアルであったことが大流行した理由であることは間違いないと思う。
しかし、こんな手の込んだわざとらしい設定をなぜ当時の人々はリアルと考えたのだろう。
大澤真幸という社会学者が「不可能性の時代」(岩波新書)のなかで、恋愛に限らず、
《理想の不可能な時代》
として1990年代以降の社会を論じている。この小説の中でも、セックスをはじめとする、人間関係の描写が実に技巧的、演技的に描かれながら、ついに「愛」に到達することができない。「いたわり」とか「やさしさ」という言葉で表すことしか出来ない関係を描いてしまっている。大沢の言う「恋愛の不可能性」を描いているといえると思うのだ。
この小説に熱中した1980年代の終わりころの人々は、その不可能性を大衆的にリアルであると納得していたのではあるまいか。そう考えると、今度の映画が、いったい何を描いているのか、実に興味深くなってくるのだ。そして、高校生諸君はこの小説をどう読むのかもね。(S) 2010/11/05
追記2019・10・05
ぼくはこの「案内」を書いた後、実はこの作品を二度以上読んでいますが、この作品について新たに考え込んでいることが二つあります。
一つ目は「蛍」という短編として発表されていますが、この作品のなかでも、かなり印象的なシーンとしてある「蛍の挿話」がこの作品中に書かれている意味はなにかということですね。
二つ目は、この小説は、語り手である、37歳の「僕」がハンブルグに着陸する寸前の飛行機の機内で「めまい」を感じるシーンから始まり、「直子」の死の後、「レイコさんとの一夜」があり、「緑」に電話するシーンで終るのですが、最初の眩暈をめぐる描写と、最後の描写の意味についてです。
僕はどこでもない場所のまん中から緑を呼び続けていた。
これが、この長編の最後の一文なのですが、「存在の場所」の、この喪失感が、この物語を語っている「僕」の意識であるとしたら、物語に登場した数人の男女は、「いったい何時、何処にいたのだろう」、そういう疑問を感じます。
作家は、ここで、何を語ろうとしているのか、結構難しいと思いますが、それについてはまたいずれという感じですね。
追記2020・10・17
棚の整理をしていると、この本が三種類出て来ました。その上、文庫版は同じ装丁が重複しています。だから計4種類ですね。なんでこんなことが起こるのでしょうね。不思議ですね。
まあ、同居人チッチキ夫人の持ち物と、シマクマ君の持ち物が一つの棚で同居しているということがありますから、これもその例でしょうが、二人とも二度づつ買ったというのでしょうか。
この作家の場合、文庫版と単行本版の重複はよくありますが、おなじ文庫を、そんなにたくさん貯蔵してどうしようというのでしょうね。不思議です。
追記2023・05・20
村上春樹が「街とその不確かな壁」という新しい作品を発表して、一応、話題になっています。「1Q84」の時のような大騒ぎになるのかと思っていましたが、さほどでもないことに、むしろ驚いています。20代の女子大生に時々会う機会がありますが、彼女たちが村上春樹を読んでいる気配は全くありません。大騒ぎから10年経って、旬を過ぎたということなのでしょうか。
映画館にたむろしているのも、村上春樹で騒いでいるのも、ジーさん、バーさんばかりということなのでしょうか。なにか、とてつもなく貧しい時代が始まっているようです。
まあ、村上春樹も、今や老作家なわけで、こんな時代に何を考えているのか、とりあえず、最後になるかもしれない新作を読んでみるしかなさそうです。読めれば、ボクの村上体験も、とりあえずのゴールです(笑)。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村





 およそ10年前、ぼくは高校生に向かって、こんなふうに「村上春樹」を語っていました。今でも、同じように感じているところがほとんどだが、少し考えが広がったところもあります。それを語り始めると、少々手間がかかりそうです。とりあえず、ぼくの2010年の「ノルウェイの森」をお読みいただければ嬉しいのですが。
およそ10年前、ぼくは高校生に向かって、こんなふうに「村上春樹」を語っていました。今でも、同じように感じているところがほとんどだが、少し考えが広がったところもあります。それを語り始めると、少々手間がかかりそうです。とりあえず、ぼくの2010年の「ノルウェイの森」をお読みいただければ嬉しいのですが。
