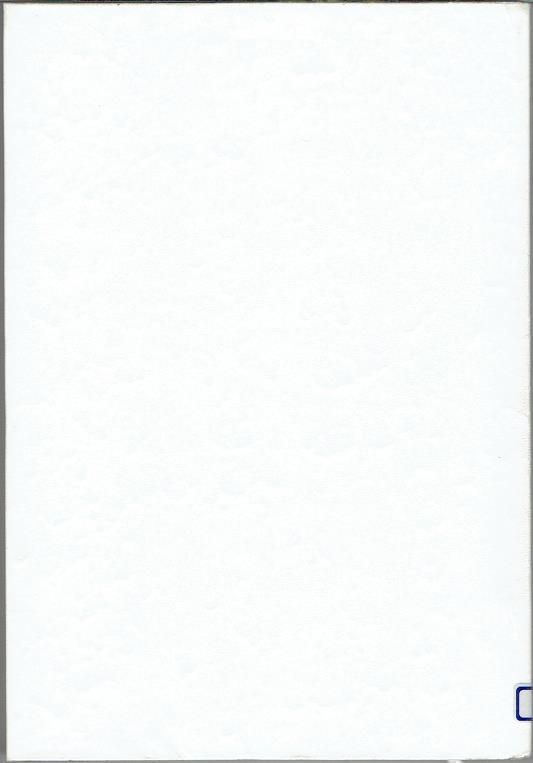菊地信義「装幀の余白から」(白水社)
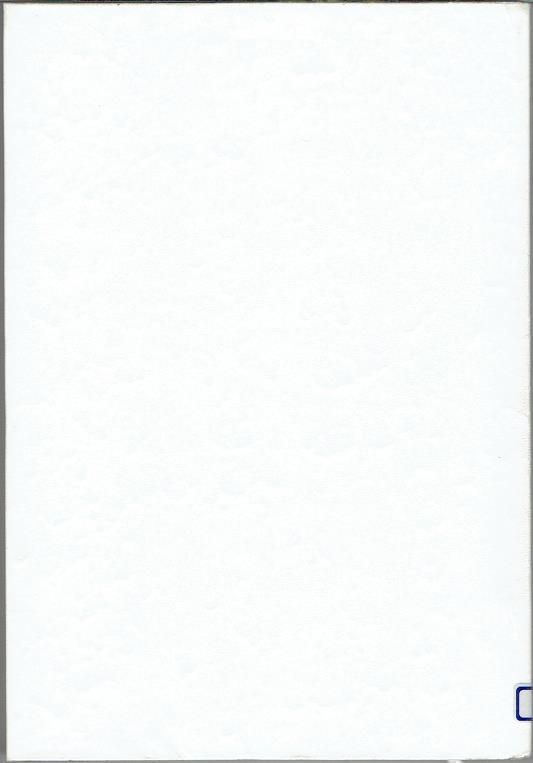
表紙だけでは、意味不明ですので、背表紙もスキャンしてみました。

装幀家の菊地信義を撮った「つつんでひらいて」というドキュメンタリーを見て「装幀の余白から」(白水社)というエッセイ集を読みました。
スキャーナーで撮ってみると真っ白く見えますが、ほんの少しグリーンのニュアンスがあるクリーム色の本です。内容は新聞や雑誌に載せた短いコラムやエッセイですね。
本に使う紙の「風合い」だとか、朝一番に飲む「コヒーの味」だとか、実際に物を作る人にしか口にできない話が、飾らない文章なのですが、どこかに「つよさ」を感じさせるところが独特の味となっているエッセイが集められています。
とはいうものの、「さあ、紹介しよう」とかまえてみると、ちょっと困ってしまうタイプの「本」です。装幀の写真をご覧になってもわかると思うのですが、限りなく特徴を消し去った、だからこそ、実に個性的な「本」の姿なのです。
書きあぐねているさなかに、作家の古井由吉の訃報がネットに出ました。「つつんでひらいて」という映画では、古井由吉自身も出演し、「自己模倣に陥らない」と装幀家の仕事をたたえていたことが印象に残りましたが、映画では、彼の「雨の裾」という短編集の装幀のプロセスが丁寧にたどられていて、それこそ、目を瞠る思いをしたことを思い出しました。
亡くなった古井由吉が生涯をかけて書き続けてきた作品の、「本」としての「身づくろい」を一手に引き受けてきた装幀家が、その作家の死に際して何を感じ、何を考えているのか、生半可な想像はできません。ただ、傷ましく思うだけです。
偶然ですが、このエッセイ集の中に、一つだけ「斯斯然然」、「かくかくしかじか」と読むのだと思いますが、その題で、古井由吉を話題にした軽妙な文章があります。
本来ならば、装幀家である菊池信義が古井由吉という作家を「物を作って生きる奥義を授かった」人であることを語っているエピソードを引用すればいいのかもしれません。しかし、それでは、古井の作品のファンであった素顔が伝わらないでしょう。こんなふうに古井由吉の作品を読んでいた一人の「読者」が彼の「本」を作っていたことを、全文引用して伝えたいと思います。
美術大学の学生に、装幀した本で、一番思いの深い一冊は、と問われ、古井由吉さんの「山躁賦」と口にし、理由を聞かれて往生した。
思いのたけは装幀にこめてあると、煙にまいてもよかったのだ。
かれこれ三十年になる。古井さんの、旅を主題とした連作小説の、編集者の一人として、取材旅行に同行する機会を得た。掲載誌に挿絵がわりの写真を撮る仕事でもあった。
原稿をいただき、真先に読み、ソエル写真を選んで、版元に渡さねばならぬのだが、読者として読みふけってしまい、仕事にならぬ。
朝から晩まで、歩き回り、同じものを眺め。飲食を共にした旅だから、作品へ取り上げられた物事に共感し、得心もいく。
対象を見極め、内から如実に掴み取った言葉で紡がれた思いや考え、現実感がある。想念が、作者自身を刺激し、あらぬ物事が想起され、古典の文言が蘇る。そんなすべてが夢や幻覚へ崩れる文のありようは壮観としかいいようがない。
「山躁賦」の文の教えは、物事の実相を見るということだ。物事は、美しくもなければ、醜くもない。実もなければ、虚もない。美醜や虚実を分つことで、世間があり、「私」ってやつも生じる。そういった世間や「私」からはぐれだし、物事と直面する。実相を見るとは、物事を、のっぺらぼうにみることだ。
物を作ることは、それに目鼻を描くことではない。発見することだ。
文芸書の装丁を生業として、数年が過ぎた頃だった。編集者から、依頼される作品を装幀するだけでなく、作者が作品を孕む時空を共にすべく、望んだ仕事。思い掛けず、物を作って生きる奥義を授かった。
後日、件の学生が、古書店で「山躁賦」を求めたが、他の小説を読むようには読めない。実相を見るといったことも書かれていない。いったい、どう読んだらいいかと、真顔で聞かれた。
具象画と抽象画があるように、小説にもある。斯斯の次第で、こんな思いや考えをいだいた。古典の文言が蘇り、幻覚が生じた理由が然然とあれば具象。読める、となる。
「山躁賦」には、そんな斯斯然然がない。
まず作者が何を言いたいのか、と考えることをやめる。
次に文章を、書かれているものや事の違いで、文の塊をほぐす。次に、塊ごとに印象を言葉にしてみる。面白い、恐ろしい。不思議、意味不明、といったあんばい。
そうして、なぜ、そう感じるのか、他人事のように己に問うてみる。引かれてある古典の文言も手掛かりになる。実際の旅であれば、おのずと解放されてある人の五感。作品を読む旅でも欠かせない。書かれてある風景から音を聞く。音の手触りを感じとる。見るものを聞く。聞こえるものに触る。そうやって紡ぎだす答えが、読者ひとりひとりの「山躁賦」だ。
「山躁賦」という作品を読むことは作者が旅したように、作品を旅することだ、その旅が、読者にもたらすのは「考える」楽しさ。物事に対して、生じる印象、なぜ、そう考えるのか、自問してみる、それが考えることのとば口だ。人は、自分で考え行動しているようでいて、案外、世間の考えを選んで生きている。
件の真顔も、この春は卒業と聞いた。さてどんな旅になることやら。
(「装幀の予覚から」所収「斯斯然然」)
いかがでしょうか。「山躁賦」という作品は、初期から中期へと、微妙な作風の変化が表れてきたころの作品集です。それにしても、菊池信義という装幀家に巡り合えた、古井由吉という小説家は、ある意味幸せな人だったのかもしれませんね。
追記2020・02・28
古井由吉の、最後の作品集「この道」(講談社)が目の前にあります。最後に収められた「行く方知れず」という作品の末尾あたりです。
皿鉢も ほのかに闇の 宵涼み 芭蕉
芭蕉の句が引用されて、最後の文章はこんなふうに記されています。
気がついてみれば、寝床の中で笑っていた。声までは立てていなかったが、物に狂へるか、と我ながら呆れた。皿鉢ばかりが白く光るのも、暑さに茹る生身が、じつはいきながらになかば亡き者になっているしるしかと思うとよけいにおかしい。
こんな笑いよりもしかし、老木が風も吹かぬのに折れて倒れる、その声こそようやく、生涯の哄笑か、未だ時ならず、時ならず、と控えて笑いをおさめた。
今、思えば、死が身近にあったことを思わせる壮烈な文章ですね。もちろん、装幀は菊地信義です。 それから映画「つつんでひらいて」の感想はここをクリックしてみてください。

 ボタン押してね!
ボタン押してね!
 ボタン押してね!
ボタン押してね!