
|
|
|
高橋源一郎「日本文学盛衰史」(講談社文庫)
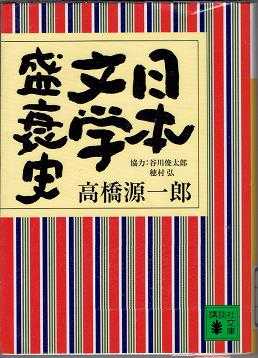 高橋源一郎の代表作の一つといっていいでしょうね、「日本文学盛衰史」(講談社文庫)を読み直しました。2001年に出版された作品で、これで何度目かの通読ですが、やはり、間違いなく傑作であると思いました。何度かこの「読書案内」で取り上げようとしたのですが、どう誉めていいのかわからなかったのです。 彼は、近代文学という「物語」を、新しい「ことば」の生成とその変転として描いているのですが、近代文学のコードから限りなく遠い「文体」で描こうとしていると言えばいいのでしょうか。そこが、感想のむずかしいところだと思います。 近代日本文学の「小説言語」は、その時代の、その言葉づかいであることによって、傑作も駄作も、おなじコードを共有し、この小説に登場するあらゆる文学者たちは、そのコードをわがものにすることで、日本文学の書き手足り得たとするならば、この小説は、そのコードを棄てることで、新しい小説の可能性を生きることができるというのが高橋源一郎の目論見なのかもしれません。 文庫本で658ページの長編小説です。第1章が「死んだ男」と題されて明治42年6月2日に行われた二葉亭四迷こと長谷川辰之助の葬儀の場に集う人々の描写から始まります。 新しい日本語で、小説という新しい表現形式に最初に挑んだ二葉亭四迷の葬儀の場には、我々がその名を知る明治の文豪たちが勢ぞろいしています。お芝居の前に、役者たちがずらりと並んで挨拶している風情ですね。そういう意味で、この場面が、この作品の巻頭に置かれているのは必然なのでしょうね。 その葬儀で受付係をしていたのが、誰あろう石川啄木でした。作家は、その場に居合わせた啄木についてこんなふうに語って、この章段を締めくくっています。 すでに訪れる者も尽きた受付で、退屈しのぎに啄木は歌を作っていた。歌はいくらでも、すらすらと鼻歌でも歌うようにできた。そして、歌ができればできるほど啄木の絶望はつのるのだった。 断るまでもありませんが、ここに登場する「啄木」は高橋源一郎の小説中の人物であり、引用された「短歌」は「啄木歌集」のどこを探しても見つけることはできません。 現代の歌人穂村弘の「偽作(?)」であることが、欄外で断られていますが、第2章「ローマ字日記」では、高橋自身の手による「ローマ字日記」の贋作が載せられています。穂村弘も「いくらでも、すらすらと鼻歌でも歌うようにでき」るでしょうかね。 この作品には、第1章の二葉亭四迷を皮切りに、漱石、鴎外をはじめ、北村透谷と島崎藤村、田山花袋などが主な登場人物として登場します。近代日本文学史をふりかえれば、当然の出演者と言っていいのですが、なぜが、啄木がこの小説全体の影の主役のように、折に触れて姿を見せるのです。 彼の有名な評論「時代閉塞の現状」は朝日新聞掲載のために執筆されたにもかかわらず、漱石によって握りつぶされたというスキャンダラスな推理に始まり、「WHO IS K」と題された、漱石の小説「こころ」の登場人物Kをめぐる章では、Kのモデルの可能性として石川啄木が登場するというスリリングな展開まであります。 何故、啄木なのでしょう。作家高橋源一郎が近代文学の相関図を調べ尽くす中で、文学思想上のトリック・スターとして啄木を見つけ出したことは疑いありません。にもかかわらず、いまひとつ腑に落ちなかったのですが、今回、読み返しながら、ふと思いつきました。 「啄木は家族と暮らしながら、どんな言葉でしゃべっていたのだろう?」 ふるさとの訛なつかし 啄木の、あまりにも有名な歌ですが、この言葉遣いはどこから出てきたのでしょうね。あるいは、近代日本文学は、いったい誰の口語で書かれていたのでしょうと問うことも出来そうです。「言文一致」と高校の先生は、ぼくも嘗ては言ったのですが、作品として出来上がった「文」は、いったい誰の「言」と一致していたのでしょう。生活の言葉を棄てた架空の日本語だったのではないでしょうか。 「ふるさとの訛」を捨て、「口語短歌」に自らの文学の生きる道を見出した啄木の葛藤の正体は、どうも只者ではなさそうですね。 高橋源一郎が、そういう問いかけを持ったのかどうかはわかりません。彼が、幾重にも方法を駆使して描いている「近代日本文学」という物語の一つの切り口にすぎないのかもしれないし、単なる当てずっぽうかもしれません。しかし、何となくな納得がやって来たことは確かです。 さて、「きみがむこうから」と題された最終章は、詩人辻征夫の きみがむこうから 歩いてきて という、引用があり、北村透谷以下、樋口一葉、尾崎紅葉、斉藤緑雨、川上眉山、国木田独歩というふうに、当時の新聞に載った死亡広告が引用されています。 斉藤緑雨は「死亡広告」を自分で書き残し、川上眉山は自殺でした。夏目漱石の死亡広告は次のようだったそうです。 夏目漱石氏逝く こうして、二葉亭の葬儀の場で始まった、ながいながい「日本文学盛衰史」は、近代文学という物語の終焉にふさわしく、登場人物たちの「死」で幕を閉じます。 このあと、作家自身の、いわば覚悟を記したかに見える結末もありますが、そこは、まあ、読んでいただくのがよろしいんじゃないでしょうか。 何だか、最後には近代文学、戦後文学のコードに回帰していると思うのですが、高橋源一郎らしいと言えば、カレらしい結末でした。 是非にと、お薦めする一冊ですが、ブルセラショップだかの店員の石川啄木や、大人向けのビデオの監督の田山花袋も登場しますが、くれぐれも、お腹立ちなさらないようにお願いいたします。   
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」] カテゴリの最新記事
|