
|
|
|
100days100bookcovers no82(82日目)
伊集院静「ノボさん 小説 正岡子規と夏目漱石」(講談社文庫) 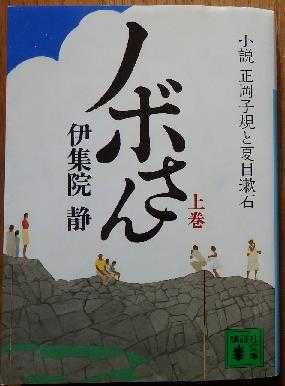 幼い頃は、本を1冊読了すること自体があまりなくて、たぶん最初に読み切ったと記憶しているのは、親から買い与えられた「ギリシャ神話」の連作集みたいなのだと思う。その後トール・ハイエルダール(という作家の名前は全然覚えていなかった)の『コンチキ号漂流記』、映画を観た後で読んだんじゃないかと思う(ほんとに読んだかはちょっと怪しい)ジュール・ベルヌの『海底二万哩』、さらにメルヴィルの『白鯨』を読んだのは小学生のいつ頃だったか、という程度。だからたぶんいわゆる絵本とか児童文学とかにはほとんど親しんでこなかった。 今回は次の作品として思い浮かべられるものが何もなかった。なかったので、その時点で読書中で、もうすぐ読み終える予定の小説とつなげられないかと安易に考える。思いつくところをネットで検索してみると「庭」でどうやらつながりそうだということで、 『ノボさん 小説 正岡子規と夏目漱石』(上下巻) 伊集院静 講談社文庫 を取り上げる。 上巻が本編260ページに、二人の関連年表付き(これは便利だった)。下巻が本編276ページに清水良典の解説が付く。2013年に出た親本は1巻だったようで、この2016年の文庫化の際に2巻に分かれた。ちなみに、2014年度第18回司馬遼太郎賞、受賞作。  小説はその後、予定通り読了。 小説はその後、予定通り読了。伊集院静を読んだのは初めてだ。といってもこの作家に特に関心があったわけではない。子規と漱石の関係に多少興味があったのだ。 でも、漱石の小説はさすがにいくつか読んでいるが、子規は俳句も歌も、さして知っているわけではない。「文学史」に出てくる二人の交友に何となく興味をもっていたという程度で、二人の交友というテーマで検索したらこれがヒットした。 サブタイトルにあるようにあくまで「小説」だから作家の想像によるところもあるにしても、当然資料に基づいているだろうから、細部は別にして大まかにはこういうことなんだろうなと理解できる。 作品は、タイトルからも想像できるようにあくまで正岡子規を描くというのが本線。そこに途中から夏目漱石が色濃く関わってくる。 作品は、二人の生い立ちや「仕事」の経緯等をほとんど知らなかったせいもあって、また、子規や、漱石を含めたその周辺が生き生きと描かれていて、とてもおもしろかった。 また、小説の地の文章は、必ずしも一般的なそれというわけではなく、ところどころに、子規を初めとする登場人物の評伝めいた説明が含まれる。これは私のような、この時代あるいは子規周辺について疎い読者には、親切でわかりやすかった。文体は特に癖もなく読みやすい。 初めは全体の流れにおもしろいエピソードを添えていけばいいかと思って書き始めたのだが、メモを取ってみたら、時間もかかったがそれ以上に分量が許容範囲を優に超えてしまったので、いくぶん方針を転換。それでも、小説自体が長く、特に下巻では次から次へといろんなことが起きるとういう事情もあって、この紹介文自体が当初考えていたものより随分長くなってしまった。面倒だったら適当に読み飛ばしていただきたい。 まずは基本情報から。 タイトルになっている「ノボさん」は、子規の幼名「升」(のぼる)に由来する愛称。本名は常規(つねのり)、最初の幼名は処之助(ところのすけ)、後に升と改名。 小説は、明治20年9月、東京銀座、路面鉄道を歩く正岡常規(以降は「子規」とする)が「ユニフォーム」を身に着けて「べーすぼーる」の試合に向かうところから始まる。 後の正岡子規、21歳の秋(小説ではそうなっているが、巻末の年表によると子規の生年は西暦では1867年[慶応3年]で、明治20年は西暦1887年、満年齢でいうと20歳)である。なかなかに映画的な冒頭シーンだ。 当時子規は、東京大学予備門から改名した第一高等中学校(後の第一高等学校)予科に在籍(その後に「本科」2年があり、さらに帝国大学へということになる)していた。 同期には、夏目金之助、南方熊楠、山田美妙、菊池謙二郎、というからすごい。この当時、子規は「べーすぼーる」に熱中している。そして、すでに俳句を作り始めている。 上巻は、ここから明治22年、子規が松山に帰省するまでを描く。「病」と「漱石」を中心にざっと紹介を。 上巻が終わるまでの期間に、子規は何度か喀血している。 明治21年8月、友人と鎌倉見物に出かけた際に、二度喀血。これが今後子規にとって宿痾となる「肺結核」の症状の始まりだった。 子規が漱石と出会ったのは、明治22年、第一高等中学校本科に上がった翌年。「落語」を評価する点で子規は漱石と意気投合する。子規は漱石に、ただの秀才ではない「本物」を見る。 同年、5月、子規は寄宿舎の自室で大量の血を吐いた。翌朝、医者が呼ばれる。医者は肺を患っていると言った。そして静養することが一番だと言って引き上げる。当時は、喀血に対する手当は、静養と栄養をつけさせることしかなかった。 おそらく「結核」だったのだろうが、作中この箇所で「結核」という言葉は使われていない。しかしWikiを確認すると「医師に肺結核と診断される」とある。ただ結核は感染症だから、本来なら「隔離」が必須のはず。当時はそのあたりが異なっていたのか、小説中ではそういう記述も見当たらない。 そんな子規を漱石が見舞いに訪れる。そこで子規が漱石に披露したのが 「卯の花をめがけてきたか時鳥(ほととぎす)」だった。そしてこれからは「子規」と名乗ると宣言する。 口の中が赤いホトトギスゆえに「鳴いて血を吐くホトトギス」と言われたのは、私でも聞いたことのあるが、それが中国の故事に由来するというのは、今回調べて初めて知った。「卯の花」は「時鳥」「子規」とともに夏の季語だが、それだけで選ばれたのかどうかは不明。 子規は「子規」以外にも、松山時代から百ほども雅号をこしらえている。「野球」と書いて「のぼーる」と読ませるものなどの中に「漱石」もある。 「漱石」は中国の『晋書』が出典の「漱石枕流」に由来するのは著名だが、「漱石」について、ここでは 子規は「筆まかせ」の中で、"漱石"という名前は今、友人の仮に名前になっていると記している。とある。 漱石は、子規を見舞った際に「七草集」を受け取り、その評を頼まれていたのだが、次に子規を会った際にその評を手渡す。その評の中で初めて「漱石」を使っている。 この他にも二人はこの時期に何度か手紙を交わし、友情は堅固なものになっていく。 病状もいくらか落ち着いたその夏、子規は松山に帰郷する。しかし移動の疲れが出たのか、帰省中、子規はまた喀血する。母・八重と妹・律は子規の血を吐く姿を目の当たりにして愕然とする。 病状を考えて、叔父の大原恒徳は、子規に、廃学、休学、まで提案している。しかし子規は、この時、到底できないと拒む。休学して仮に五年、十年長生きしても、決して満たされることはない、と。子規はこの頃から、自身が長く生きられなことをすでに覚悟していた。 ここまでが上巻。 下巻は、明治25年年頭から始まる。 子規は、明治以前の俳諧を系統立ててまとめてみようと考えていた。その理由のうちの一つが、東京でも子規の世話人の一人である陸羯南(くがかつなん)の発行する新聞「日本」から執筆依頼がきていたことで、俳句・短歌の欄を作ることも考えていた。 子規は俳諧の歴史、俳人の洗い出し、さらに俳人の系統を系譜としてまとめようとした。これを全部一人でやろうとしたのである。 子規はもう大学の学業に励むことに興味と関心をすっかり失っていた。 漱石はそんな子規を心配し、あれやこれやと世話を焼くが、子規は耳を傾けなかった。 結局、子規は帝国大学を退学する決心をする。 世話人である陸羯南はじめ、何人かに子規は「退学」の決意を伝え、反対する相手を説得した。彼らが最終的に了承せざるをえなかったのは 子規の口から、自分の将来の時間はさして長くないので、今、自分がやりたいことをしておきたい、と言われたからである。 子規は大学を辞めて、陸羯南が主宰する新聞「日本」で働くことになった。そして郷里から母・八重と妹・律を呼び寄せる。 明治27年、終生の地となる根岸の家に転居する。いわゆる「子規庵」である。 同年、日清戦争が勃発。子規は「俳句分類」をやり遂げたいと考えながら、一方で、早く海を渡って従軍記者として仕事をしたいとも思う。こんな病状にもかかわらず。陸羯南が子規の従軍への懇願に容易に首を縦に振らなかったのは当然のことだ。激しい喀血はなかったが、疲労によって寝込んでしまいことが度々あり、従軍は常識的には無理な話だった。ただ子規はいったん言い出せばきかない。子規はとうとう戦場で死んでも本望だとさえ言い出す。 結局子規に押し切られる形で陸羯南は子規が戦地に赴くことを認める。戦況が落ち着いていたということもある。 子規は明治28年4月、遼東半島に渡るが、その2日後には日清講話条約が結ばれる。砲撃の音などどこからも聞こえない。結局子規の渡航は、物見遊山の旅となる。しかし、この地で子規は、第二兵站(へいたん)軍医部長に着任していた森鷗外に会う。鷗外はすでに訳詩集「於母影」や小説「舞姫」を発表していた。子規は鷗外と清国を離れるまで毎日のように会い、俳句について語り合い、創作もした。 5月、子規は帰途につく。しかし帰りの船でまたしても喀血。喀血はなかなか止まらなかった。ようやく神戸に着いたが、また喀血が始まる。記者仲間に助けられてようやく入院。 碧梧桐を通じて知り合い、数年前から文通をしていた高浜虚子も京都から見舞いに来た。当初病状は悪かったが、徐々に回復に向かう。母・八重も到着する。 漱石は同じ頃、愛媛県尋常中学校教諭に就任。 子規は8月退院。漱石の家で50日あまりを過ごす。松山から東京に帰る途中、子規は一度、神戸に寄り、医師の診察を受ける。汽車旅行に差障りなしと言われる。その後、大阪へ。しかし腰の骨が痛み始め、歩くこともかなわぬようになり大阪で数日休む。さらに奈良へ。宿は、小説では「角定」(かくさだ)とあるが、一般的には「對山楼」(たいざんろう)として知られていたようだ。一流の宿とのこと。旅費は漱石から借りた十円。しかも後に子規は漱石への手紙の中で、その金を初日にすべて使い果たしたと書いている。 そしてこの宿に4泊した際に、あの 柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺等を詠む。そのことから、現在、宿の跡地にできた日本料理店「太平倶楽部」と、子規の親戚で、造園家で樹木医でもある正岡明が2006年に作庭したのが「子規の庭」と呼ばれるということらしい。まぁ「庭」に関しては、こじつけもいいところではあるが、どうかご容赦を。 東京に戻った子規だが、喀血はおさまっていたが、腰の痛みは悪化していた。リュウマチの疑いがあるとして医者を呼んだが、医者の診断はリュウマチではなかった。 医者は専門ではないから断定はできないが、結核菌が広がって進行するカリエスではないかと言う。カリエスは結核性脊椎炎のこと。子規の場合は腰椎に症状が出た。進行すると椎体内が壊死し膿の巣ができる。すぐに専門医が呼ばれ、手術が決まる。しかし手術を終えて一週間後、また腰や背中が痛み始めた。膿も出始める。それは以降死ぬまで続くその処理は律がするようになった。 明治29年、松山の柳原極堂が子規に句誌について相談の手紙を寄越していた。名前は「ホトゝギス」。相談を重ねるうちに、句誌は子規の主宰という形になっていった。明けて明治30年「ホトゝギス」刊行。 明治29年に熊本の高校に移った漱石は同年、鏡子と結婚。しかし流産を経て、31年鏡子は入水自殺を図る。しかし翌年に夫婦は女児を授かる。 明治30年、熊本の漱石から、教師を辞めて文学に向かいたいと手紙が来る。七月、漱石、帰京。小説の構想を練り始めていた。 松山で「ホトゝギス」がなかなか売れないことから、柳原極堂が一人ではもうできない、廃刊したいと子規に泣きつく。子規は虚子に手紙を書く。二人で建て直したいと頼む。虚子はこれを承諾。 明治31年、松山版を引き継ぐ形で東京版「ホトゝギス」刊行。 明治31年新聞「日本」で子規は「歌よみに与ふる書」と題する批評文を掲載。紀貫之や『古今和歌集』を「下手な歌よみ」「くだらぬ集」と論じた。反論が押し寄せ、再反論等のための批評が十回も続く。子規は自身の創作も掲載し、開かれた場になる。「歌よみに与ふる書」は多くの支持を得た。これを機に伊藤左千夫や長塚節が子規の元に集い、やがて「アララギ派」が誕生する。 子規の『俳諧大要』が明治32年1月「ホトゝギス」の発行所から刊行。「ホトゝギス」は売れ始めたが、虚子は多忙になり、やがて病に倒れる。急性大腸カタル。子規は碧梧桐を中心に発行を継続するように頼む。 子規はこんな病状でも多忙だ。「ホトゝギス」の原稿のため短歌会、句会が数日置きに催される。すべての中心に子規は座し、時に「輪読会」もやる。何人かは子規庵に泊まる。短歌会、句会の間の来客も多い。「日本派」「歌よみに与ふる書」等の影響もあり全国から人が来る。漱石の紹介で寺田寅彦も来た。"蕪村忌"には子規庵二十一畳半に46人が入った。 明治33年、漱石のイギリス留学が決まり、7月、熊本から上京、子規庵を訪問する。8月、子規は喀血。清国からの帰途での喀血以来の量だった。 漱石が留学の前に再度子規を訪れる。留学の期間は2年だが、準備等を入れると2年半はかかる。子規も漱石もこれが最後だとわかっていた。ぎこちない表情が二人に浮かぶ。子規は 独り悲しく相成申候 と「ホトゝギス」に書いた。 子規の容態は次第に悪くなる。激しい喀血はないが、発熱があると起き上がれないようになり、句会、歌会も中止になることが多くなった。それにつれて子規は「我儘」も強くなる。身内だと思わている碧梧桐や虚子、さらに母八重や妹律には殊に。 この年の"蕪村忌"は、子規は容態が悪く皆と連座できず、恒例の記念撮影も子規以外で行われた。翌日、子規一人だけで写真を撮ることになった。少し趣向を凝らしたいという写真屋の申し出に応じて横顔で撮影された。このときの写真が教科書等でおなじみのあの子規の写真である。 子規の病状が進み、膿をぬぐう時の痛みに耐えかね子規は大声を出したり、救いを求めたりする。世話をする律はそれを聞きながら世話をし続けた。子規が錯乱状態に陥るときは、母妹の手に負えず、隣家の陸羯南を呼んでくる。それでようやく子規の錯乱はおさまるということもあった。 明治34年、子規は漱石に 僕ハモーダメニナッテシマッタという書き出しの手紙を書く。この手紙が漱石の元へ届いたのは40日後。漱石は子規に返事を書く。 この手紙の交換が、二人の手紙での交わりの最後だった。漱石はロンドンで、しかし、疲れ果て、不愉快になり、孤独になっていった。 翌明治35年、強い麻痺剤で何とか抑えていた痛みは、何度も服用が必要にになっていった。 新聞「日本」で「墨汁一滴」「病牀六尺」を書き継ぎ、私的には「仰臥漫録」も残す。 夏は何とか越せた。9月、子規の足の甲がひどくふくらんでいることに律が気づく。水腫だった。医師は血液の循環が悪くなっているためだと言った。激痛もともなう。モルヒネも効かない。子規は容態がこれまでとは違うことに気がついていた。 9月18日、医師が呼ばれ、陸羯南も来て、碧梧桐も呼ばれる。 「高浜も呼びにおやりや」 子規が言う。子規自身が何か感じている。 糸瓜咲て痰のつまりし仏かな 最後の句が辞世の句になった。へちまの水は旧暦の八月十五日に取るのをならいとする。それができなかった無念を句に詠んだのだった。子規は昏睡に入る。その後2度目ざめ、 「だれだれが来ておいでるのぞな」 と律に訊いた。それが最後の言葉になった。 翌9月19日未明、時折うなり声を上げていた子規が静かになり八重が手を取ると、手はもう冷たく、呼びかけても反応はなかった。 様々な人が訪れ子規と「対面」していった。 ふと訪れた静寂の中で、八重は、息子の両肩を握りしめ顔を上げるようにし、両肩を抱くようにして言った。 「さあ、もういっぺん痛いと言うておみ」 それは月明かりの中で「透きとおるような声で響き渡った。」「八重の目には、それまで客たちが一度として見たことのない涙があふれ、娘の律でさえ母を見ることができなかった。」 9月21日、葬儀。150余名の会葬者の中で行われた。田端の大龍寺で土葬が執り行われた。戒名は「子規居士」。子規の死を報告した「ホトゝギス」を送り、続いて碧梧桐と虚子が、子規の死を知らせる手紙をロンドンの漱石に書き送ったのが10月3日。漱石がこの手紙を受け取ったのが11月下旬だった。 漱石は句を作る。 筒袖や秋の柩にしたがはずこれらを虚子宛の手紙に書いて送った。 漱石は、翌明治36年に帰国。東京帝国大学、明治大学の講師を務めながら、38年に「ホトゝギス」に最初の小説「吾輩は猫である」を発表。 漱石のこれ以降は皆さん、ご存知の通りである。 松山でも東京でも、子規は人に慕われ人を慕った。人の誘いを断れない性格もあって子規の周りにはいつも子規を慕う人の輪ができていた。子規が残した最大のものは「人」だったのだろう。 さらに作家は、明治という時代が、子規のような「自分の信じたもの、認めたものにむかって一見無謀に思える行為を平然となす」人物を生んだのではないかという。 子規の人となり、性格については、無類の大食漢であるとか、金銭に無頓着で、子規が大学を辞めて八重と律を東京に呼び寄せる際の「旅行」に、57円40銭という、松山なら親子3人が半年以上暮らせる額を平気で費やして呆れられても、金銭への無頓着さは生涯変わらず、漱石に対しても同様だったが漱石はそれを許容していたとか、子規の淡い恋愛感情とか、おもしろいエピソードはたくさん出てくる。どこまで「脚色」されているかは別にして。 彼ら二人には、一度心に決めると「一直線に突進する」という似たところがあった。が一方でその振る舞い方は随分違っていた。 子規は、言ってみれば、死ぬまで、やりたいことを、やるべきことを追究し続けた。病を得てそれに一層拍車がかかった面もあるだろうが、いずれにしろそういう意味では「子ども」でいることを選び、最後までそれを貫いた。衝動と直観に従った生き方と言える。だからこそあれだけの仕事ができた。 一方、漱石は、周囲の「期待」を飲み込んで「合理的」に行動し、許容できる限り許容した上で、最終的に「文学」に向かい、小説を書いた。漱石は、子規より少なからず「屈折」し、だからこそ「小説」で評価されたということかもしれない。 作家は、この違いは、二人の生い立ちも関係していると書いている。 「周囲の期待を一身に背負って育てられてもなお自由に自分の道を探し続ける子規と、生まれてすぐに里子に出され、その後も養子にやられ、大人たちのゴタゴタの中でも自分を探し続けようとした金之助はまったく相反する環境で育った。」 そしてそんなふうにお互いが随分違うからこそ、二人は惹かれ合った。それはもしかしたら奇跡的なことかもしれない。子規がいなければ、もしかしたら漱石もいなかった。 ということで、随分長くなってしまいました。 では次回、DEGUTIさん、よろしくお願いいたします。2022・03・05・T・KOBAYASI 追記2024・05・11 投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)(51日目~60日目)(61日目~70日目)(71日目~80日目) (81日目~90日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。   
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.09.15 09:47:18
コメント(0) | コメントを書く
[読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」] カテゴリの最新記事
|