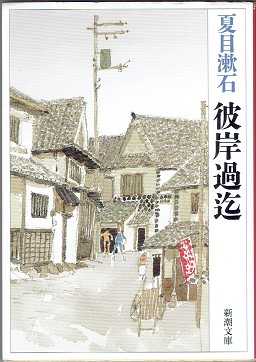夏目漱石「彼岸過迄」(新潮文庫)(その1) 久しぶりに夏目漱石の「彼岸過迄」(新潮文庫)を読んでいます。1912年ですから、明治天皇が59歳で亡くなった年です。明治45年ですね。で、大正元年です。その年の1月1日から4月29日まで、朝日新聞に連載された作品だそうです。明治天皇の命日は7月30日ですから、文字通り、明治時代に書かれた最後の小説ということになります。
ちなみに明治天皇の誕生日は1852年の11月3日です。もちろん、生年は違いますが、わが家の同居人と同じ誕生日です。というわけで、我が家では、毎年、明治の「天長節」を祝ってきたわけです(笑)。
で、「彼岸過迄」に戻ります。読むのは初めてではありません。実は、神戸の地震があったころから続けている、毎月1度の「本読み会」に参加しているのですが、そこの課題になったので、久しぶりに読みはじめました。
棚にあった古い文庫本で読み始めたのですが、黄ばみがひどくて、今のボクの視力では通読不可能なことを悟って本屋さんで新しい新潮文庫を買ってきました。カバーの絵は安野光雅で、解説は柄谷行人でした。ページも美しくて(当たり前ですが)、活字も少し大きくて、これなら読めると、勢い込んで読みはじめましたが、なかなか進みません。
今読んでいるのはこのあたりです。
彼は久しぶりに下谷の車坂へ出て、あれから東へ真直ぐに、寺の門だの、仏師屋だの、古臭い生薬屋だの、徳川時代のがらくたを埃といっしょに並べた道具屋だのを左右に見ながら、わざと門跡の中を抜けて、奴鰻(やっこうなぎ)の角へ出た。
彼は小供の時分よく江戸時代の浅草を知っている彼の祖父さんから、しばしば観音様の繁華を耳にした。仲見世だの、奥山だの、並木だの、駒形だの、いろいろ云って聞かされる中には、今の人があまり口にしない名前さえあった。広小路に菜飯と田楽を食わせるすみ屋という洒落た家があるとか、駒形の御堂の前の綺麗な縄暖簾を下げた鰌屋は昔から名代なものだとか、食物の話もだいぶ聞かされたが、すべての中で最も敬太郎の頭を刺戟したものは、長井兵助の居合抜きと、脇差しをぐいぐい呑んで見せる豆蔵と、江州伊吹山の麓にいる前足が四つで後足が六つある大蟇(おおがま)の干し固めたのであった。それらには蔵の二階の長持の中にある草双紙の画解(えとき)が、子供の想像に都合の好いような説明をいくらでも与えてくれた。一本歯の下駄を穿いたまま、小さい三宝の上に曲(しゃが)んだ男が、襷がけで身体よりも高く反そり返った刀を抜こうとするところや、大きな蝦蟆の上に胡坐をかいて、児雷也が魔法か何か使っているところや、顔より大きそうな天眼鏡を持った白い髯の爺さんが、唐机(とうづくえ)の前に坐って、平突(へいつく)ばったちょん髷げを上から見下ろすところや、大抵の不思議なものはみんな絵本から抜け出して、想像の浅草に並んでいた。こういう訳で敬太郎の頭に映る観音の境内には、歴史的に妖嬌陸離(ようきょうりくり)たる色彩が、十八間の本堂を包んで、小供の時から常に陽炎っていたのである。東京へ来てから、この怪しい夢は固より手痛く打ち崩されてしまったが、それでも時々は今でも観音様の屋根に鵠の鳥とりが巣を食っているだろうぐらいの考にふらふらとなる事がある。今日も浅草へ行ったらどうかなるだろうという料簡が暗に働らいて、足が自ずとこっちに向いたのである。しかしルナパークの後ろから活動写真の前へ出た時は、こりゃ占い者などのいる所ではないと今更のようにその雑沓に驚ろいた。せめて御賓頭顱(おびんずる)でも撫でて行こうかと思ったが、どこにあるか忘れてしまったので、本堂へ上あがって、魚河岸の大提灯と頼政の鵺(ぬえ)を退治ている額だけ見てすぐ雷門を出た。敬太郎の考えではこれから浅草橋へ出る間には、一軒や二軒の易者はあるだろう。もし在ったら何でも構わないから入る事にしよう。あるいは高等工業の先を曲って柳橋の方へ抜けて見ても好いなどと、まるで時分どきに恰好な飯屋でも探す気で歩いていた。ところがいざ探すとなると生憎なもので、平生は散歩さえすればいたるところに神易の看板がぶら下っている癖に、あの広い表通りに門戸を張っている卜者(うらない)はまるで見当らなかった。敬太郎はこの企図(くわだて)もまた例によって例のごとく、突き抜けずに中途でおしまいになるのかも知れないと思って少し失望しながら蔵前まで来た。するとやっとの事で尋ねる商売の家うちが一軒あった。細長い堅木の厚板に、身の上判断と割書わりがきをした下に、文銭占いと白い字で彫って、そのまた下に、漆で塗った真赤な唐辛子が描かいてある。この奇体な看板がまず敬太郎の眼を惹ひいた。(P89~P90)
「停留所」と題がつけられた、二つ目の章(?)の途中です。なぜ進まないかというと。面白くないからではありません。面白すぎて前に行かないのですね。
なんというか、それでどうなるのかと急き立てるものがないのです。引用したところも、多分これで、連載一日分くらいなのですが、主人公の田川敬太郎という、まあ、立派に(?)大学は出たけれど、高校生向けの国語便覧とかでは高等遊民とか呼ばれている、マア、はっきり言えば、することのない暇人が、これからどうしようというので「卜者(うらない)」、易者ですね、それを探して、浅草あたりにやってきているシーンなのですが、退屈ですか?面白いと思いませんか。
ぼくは、この年になって読み返していて、こういうところが面白くてしようがないのですが、これは過去に、何度か読んだときにはなかったことです。二十代で初めて読んでから、漱石の長編の中では割合好きな作品で、10年に一度くらいのテンポで読み返した記憶がありますが、やはり、須永と千代子の話として覚えていました。
ところが、今回読み返していて、こういうところに立ち止まるというか、たたずんでしまうのです。たとえば、ぼくには、今、東京で暮らしていらっしゃる学生時代からの友人とかがいらっしゃるのですが、中には引用している場面の近くに住んでいらっしゃる方もいたりするわけで、その、彼なり彼女が、例えばこのシーンをお読みなれば、その当日だか、次の日だか、この辺りをウロウロなさるに違いないとか思い浮かんでしまって、まあ、テキパキ前には進まないまま「今日はこの辺りで」ということになってしまうわけなのです。
なぜそうなるかというと、敬太郎のことを語っている語り手の態度がそうだからだと思うのです。筋をはこぶ気があまり感じられないというか、一つ目の章(?)の「風呂のあと」では、マア、考えてみれば「風呂のあと」なんて、つけられている題も題なのですが、敬太郎と同じ下宿の住人で、結果的には下宿代を踏み倒して、満州くんだりに夜逃げしてしまう森本という男が出てきますが、そこで語られるのは彼が残していったステッキとか盆栽のことばかりだったのですが、読み手のぼくの頭には下宿の傘立てだかに、主を失ってずっと立てかけられているステッキのイメージが、なぜか鮮やかに残ってしまうのでした。
多分、漱石がそういう書き方をしている。あるいは、そういう語り方で読み手に聞かせている。そのことに、なんとなくではあるのですが、反応する年齢になったということかもしれません。で、ふと思うのは、退屈極まりなかった「吾輩は猫である」を読み直してみてもいいなということでした。
いや、しかし、「猫」を書いたときに彼は38歳くらいで、この作品の時には45歳ですね。うーん、年齢とかの話とは少し違うのかもしれませんね(笑)
とりあえず、今回(その1)はここまでですが、「彼岸過迄」については(その2)に続きます。