
|
|
|
カテゴリ:読書案内「昭和の文学」
100days100bookcovers no86 86日目
川端康成「雪国」(新潮文庫) YAMAMOTOさんから『長崎ぶらぶら節』の紹介があったとき、ちょうど買ったばかりの本がありました。偶然ですが、「芸者」という要素で繋がっていたので、今回はこれでいくことにします。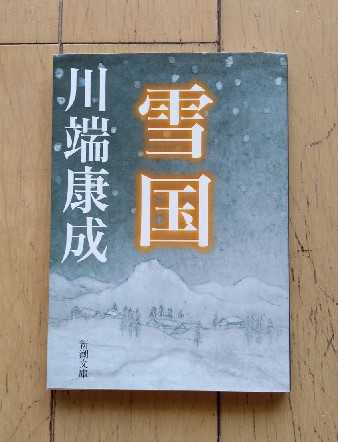 『雪国』(川端康成著、新潮文庫) 昭和10年から書き始められたこの作品の、「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった」という冒頭文は知っていても、読んでいる人は案外少ないのではないでしょうか。もしかしたら、若い人の中には、川端康成がノーベル文学賞を受賞したことを知らない人もいるかもしれません。教材になるような小説とも思えませんし、現代社会で頻繁に参照されるような内容でもありません。ですが、何度も映像化されていることを思うと、なにか人をそこへ回帰させるもの、惹きつけるものがあるのだと思います。 じつは、本を買う少し前、高橋一生の島村、奈緒の駒子でドラマ化されたNHKの作品を観ました。小説とドラマ(小説と映画もですが)は別のものなので、ドラマを観て原作を読みたいと思うことはあまりないのですが、このときは「久しぶりに原作を読んでみようかな」と思ったのです。このドラマでは、芸者の駒子の来し方を、彼女の口から聞いたシーンとして繋いで、主人公の島村の想念のような形でドラマの最後の方で見せたのですが、「現代ではこんな説明シーンが必要なほどわかりづらい内容なのか」という思いと、おそらく原作では、人物たちの言動と心理だけで描かれていたはずだという思いが重なって、ふと原作を読みたくなったわけです。 私は、小説読みとしてはわりに早熟だったので、この小説は中学生のときに読みました。人生の早い時期に大人の小説を読むことの弊害は、そこに描かれている心理や機微を理解できないまま、「読んだ」という事実だけを抱えて大人になり、小説のほんとうの面白さを知らないで終わってしまうことです。中年になって読んだ漱石の『三四郎』の面白さに呆然としたとき、そのことを痛感しました。 『雪国』もそうです。「日本的な抒情小説」と若い私の中で固定化していたイメージは一気に覆りました。これは、「人生のすべてを徒労だと思うように生きてしまった」島村が、駒子の命の生々しい輝きに触れ、その美しさ、哀しさに惹かれてゆく過程を島村自身が冷徹に見つめている「心理小説」です。ただ、川端の文章力、表現力が怖ろしほど鋭敏で叙情的な感覚で支えられていて、それが島村の冷徹さを和らげているだけで、島村の空虚さや周囲への距離感は終始一貫して小説の中に存在しているのです。 島村の中にある「徒労感」「周囲への距離」がどこから来たのかは、小説の中ではっきりとは描かれていません。ですが、幼くして家族を次々に失い、16歳で最後の親族になった祖父を看取って天涯孤独になった川端の体験を抜きに考えることはできないと思います。10代でひとり祖父の介護をした川端は、今で言う「ヤングケアラー」でした。処女作の『十六歳の日記』は、このときの介護の体験を書き綴ったものです(この作品も同時期に読みましたが、今のこの年齢で読み返したいところです)。生家がそれなりに裕福だったのでお金には困りませんでしたが、子どもの頃に親しい人の「死」をいくつも見てしまったことは、「死」を近くに感じること、「生」の実感や喜びをつかみにくいことと無関係ではないでしょう。もちろん個人差はあるでしょうが、川端少年にとっては大きな空洞になっていったのだと思います。 ですが、この島村の「距離感」は、私にとっては決してイヤなものではなく、むしろ好ましいものでした。こういう男性と実際に付き合いたいかどうかはまた別の問題ですが、深い関係になった駒子を引かせて自分のものにするでもなく(そんな財力もなかったのだろうけれど)、足繁く北国の温泉に通ってくるでもない、しばしば駒子から責められる島村の「フラットさ」は、旧弊な男性性からほど遠く、近代人の病のようなものでもなく、島村の頭でっかちな想念を身近なことばでひょいと「人生の真実」として呟いてしまうような駒子の人間的魅力を引き出します(川端自身はこのことを「島村は私ではありません。男としての存在ですらないようで、駒子をうつす鏡のようなもの、でしょうか」と語っているそうですが)。 なかでもことに好きだったのは、三味線の音で駒子の強い生命力を思わせる描写でした。 ***** 島村の「視線」は、駒子の妹分である葉子にも向けられ、駒子よりもさらに激しい「何か」を感じ取ってたじろぎます。島村の中の空洞は、葉子の幼い直情を入れたが最後、持ちこたえられないのでしょう。ラストは、島村が駒子と天の川を見つめていると遠くで火事が起こるのですが、火事に遭った葉子が建物から落下し、葉子を胸に抱える駒子に島村が駆け寄ろうとするシーンで終わります。手が届きそうで届かない、ホッと安らぐことのないラストシーンですが、 「踏みこたえて目を上げた途端、さあっと音を立てて天の河が島村の中へ流れ落ちるようであった。」 と結ばれた掉尾の一文に身を任せるしかなく、そうすることで、この作品は、永遠に解けない謎のように読者の中に残り続けます。 島村から見た駒子と葉子の関係については、もっと読み込まないと書けないのですが、長くなりそうなので、それはまた別の機会に。現代社会ではこの小説が積極的に読まれるようなモチベーションはなかなかないかもしれませんが、清澄な自然と人間の心の深淵が同時に描かれている「純粋さの物語」として、読みたいときにそこにあってほしい、私にとっては心の何処かが欲するようなものなのだと思います。 それではKOBAYASIさん、お願い致します。K・SODEOKA・2022・05・30 追記2024・05・16 投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)(51日目~60日目)(61日目~70日目)(71日目~80日目) (81日目~90日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。   
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.05.18 00:37:30
コメント(0) | コメントを書く
[読書案内「昭和の文学」] カテゴリの最新記事
|