
|
|
|
大江健三郎「読む行為」(大江健三郎同時代論集5・岩波書店)
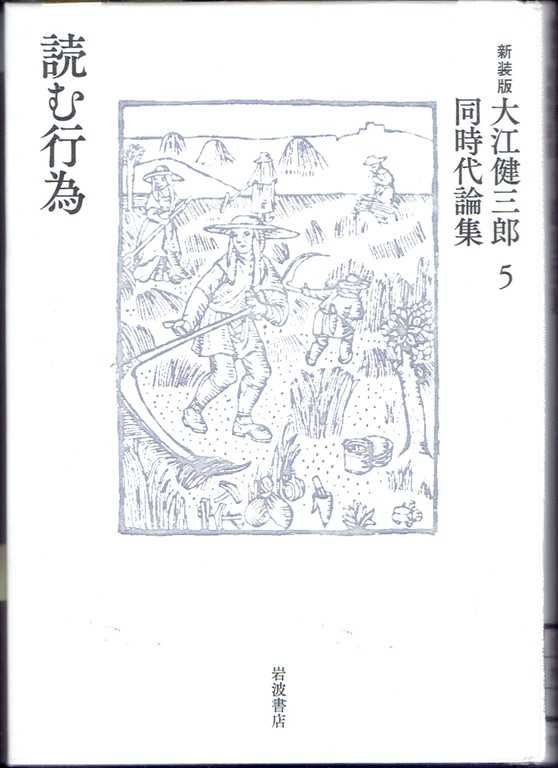 1980年代に、一度、「同時代論集」と銘打って出されていたシリーズの新装版のようです。全部で10巻あるようですが、この第5巻は、多分、1970年ころに「壊れものとしての人間」(講談社)として出版され、その後、講談社文庫、講談社文芸文庫に収められていた長編評論と、単行本としての記憶がないまま、以前の同時代論集にはいていた「アメリカ旅行者の夢--地獄にゆくハックルベリイ・フィン」と、同じく「渡辺一夫架空聴講記」の三つの評論が収められていますが、いずれも1969年ごろ「群像」とか、岩波の「世界」とかに連載されていた文章です。 「壊れものとしての人間」は講談社の単行本で、「地獄に行くハックルベリイ・フィン」は図書館のバックナンバーで読んだ記憶がありますが、まあ、40年以上も昔の話ということもあるのでしょう、内容は何も覚えていませんでした(笑)。 図書館で、作品掲載雑誌のバックナンバーまで探すとかいうと、かなり入れ込んだファンのように思われるかもしれませんが、大学に入ったばかりのころのことで、すでに新潮文庫で出ていた「セヴンティーン」(新潮文庫)の続編で、「文学界」という文芸雑誌には発表したけれど、本としては出されなかった「政治少年死す」という作品が、「文学界」のバックナンバーなら読めるとかいうことが、数少ない「話が合う」友だちとの間で話題になって、二人で図書館をウロウロしたことも、ボンヤリ覚えています。まあ、50年前、そういう年頃で、そういう時代でしたね(笑)。 「大江の評論はダルイよな!」 それが、その友達との合言葉でしたが、小説だって、当時、出版されたばかりで、 「スゴイ!スゴイ!」 と騒いでいたことだけは覚えている「万延元年のフットボール」(講談社文芸文庫)とかを、最近、読み直して驚きましたが、何を喜んで読んでいたのか、今となっては見当がつかないわけですから、クドクドと、やたら一文が長い評論なんて、自動的に字面を追っていただけで、今となっては、何にも残っていませんね。 で、今回、まあ、ヒマに任せて読み直していて、こんなところにハッとしてしまいました。 ぼくがしばしばくりかえしてきた愚かしい泥酔さえも、時にはそうした指向にみちびかれていたことがあった。誰もいない書斎で、あるいは旅さきのホテルで、ぼくはおよそ嫌悪感とともにしか、その味を認識しえない強い酒によってひとり猛然と酔いはじめる。その酔いの上昇のさなかに、ぼくは頭のなかの火のかたまりに熱せられてしだいに赤く浮かびあがってくるタングステン・コイルで示されるような、はっきりした分岐点の存在を見出す。それはAの道を選択するならば、この暴力的な自己破壊じみた乱酔をなおも加速して、それがついににせの情熱すぎないにしても、ともかくその昂揚のうちに死ぬ、あるいは意識が存在しなくなるのであり、Bの道を選択するならば、再びここから醒めておよそ額をまっすぐにあげることもむつかしいような憂鬱の明日にはいりこむのであるところの分岐点である。アルコール飲料の眠りをさそう性格によってぼくの実験はなんとか無難にすんできたといっていいかもしれない。泥酔したあげくの眠りは、死に似ているし、二日酔いの憂鬱は、狂気のさめたあとの脱力感をいくらかなりと想像させる。もともとぼくは、活字のむこうの暗闇から自分を無意味に引き剥がすところのアルコール飲料を、二十代の半ばちかくまで嫌悪していた。それが不意に、ウイスキーあるいはジンに向かって急速に近づくことになったのは、狂気あるいは死に準じるものについてひとつの体験に近いように思える状態を、想像力のヒューズが焼けきれるような電圧まで忍耐せざるをえなかったとき以後なのであるから(もっとも忍耐しえた以上、ぼくはもとより死も、狂気も経験しなかったわけだ)、ぼくの頭のコンピューターの配線図は、アルコール飲料と無意識との接続について単純な直線を描いているにちがいない。(P159)実は、昨年の夏、具体的にいえば2023年ですが、「芽むしり仔撃ち」(新潮文庫)という、1950年代の末に書かれた、今となっては大江健三郎の初期を代表する作品を読みあって感想をいうという会がありました。はい、読書会ですね。そこで、その作品の主人公の少年の、結末における絶望的状況ということが話題になりました。 その作品で、読んだ方はご存知でしょうが、作家が「このままだと主人公の少年は死ぬほかはない。」という、まあ、絶望的結末を描いていることに対して、作品の価値を疑うかの違和を唱える方がいて、その意見を聞きながら、ボクの中に広がっていったのは 「それはちゃうんちゃうかなあ!?」 という気分でしたが、ふと、湧いた、その拒絶感を説明することができませんでした。 で、偶然、この文章に出会ったというわけです。本文は「芽むしり仔撃ち」の執筆から、ほぼ、10年後の1968年、「皇帝よ、あなたに想像力が欠けるならば・・・・」と題されて「群像」に発表されたエッセイの、ほんの部分ですが、いかがでしょう、彼は絶望していたのではないでしょうか。 彼にとって「状況」を描くということが 狂気あるいは死に準じるものについてひとつの体験に近いように思える状態を、想像力のヒューズが焼けきれるような電圧まで忍耐せざるをえなかった 行為であったという述懐だとボクは読みましたが、その結果生まれた、この時代の作品群が、おおむね 絶望的な状況に投げ出された人間 を描くことになったことは、作品を否定する理由には、やはり、ならないし、当時、読者であったボク自身を含めて、多くの読者たちは、作家のその状況認識をこそ支持したのではなかったか、というのが、この文章を読んでハッとした理由のように感じました。 ただ、たとえば、ここで自らのアル中の危機と想像力のぶつかり合いを持ち出して語られる大江の「絶望」の語り方を、当時、20代だったボクたちはだるい!と思っていたようなのですね。 というわけで、ボクのような「同時代」を、なんとなく知っている年齢の読者は、どうしても、その時代に引き戻されてしまう、いわば、古色蒼然とした「同時代論集」なのですが、もっと、若い、これから、ひょっとしたら大江健三郎とか読むかもしれない人たちが、どこをどうお読みになるのか、そういう興味も浮かんできた評論ですが、読みでがあることは疑いないと思いましたね。 まあ、初めてこの本で大江に出会うのは、チョット、無理があるとは思いまうがね(笑)。    お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.02.15 11:23:17
コメント(0) | コメントを書く
[読書案内「大江健三郎・司修・井上ひさし・開高健 他」] カテゴリの最新記事
|