
|
|
|
カテゴリ:読書
中山昌亮「不安の種+」(少年チャンピオンコミックス)を読んだ。
何でいきなり続編から読むのか……って、細けぇこたぁいいんだよ!! 一話完結形式だからどこから読んでも問題は無いのさっ。 不条理系ホラー漫画として近頃とみに名高い同作だが、「傑作」の二文字が相応しいのではないかと思う。 思うに、「漫画」という媒体における最大の利点は「絵」の存在である。 眼前にて展開される事象を静止画として完全に写し取るだけなら写真が最高であることは言うまでも無い。けれども漫画に代表される「絵」の媒体は、写実的事象に加え現実に有り得ないであろう光景までも緻密に描写することができる。それは対象の美醜に関わりなくそうなのだが、ともかくも、「漫画」の利点を最大限に生かし切ったのがこの作品ではないだろうか。 例えば我々が何気なく蝉の声を聞きながら、暑気の充満する夏の道を歩いているとする。額をなでる汗を鬱陶しく感じつつ、手のひらで顔を拭う。おや、そういえばハンカチをわすれてしまった。ぬるぬるとした一抹の不快が手に宿ってほどなくして消える。さっきまで居たコンビニは実に涼しかったが、これから冷房の利く家に帰るまでの辛抱だ……そんな、どこにでもある日常の風景を行くとする。 しかし、別段、何のこだわりも興味も無いままに地面に視線を降ろすと、そこには今まで見たことも無いようなグロテスクな芋虫が居る。黒や茶や、そのほかまるで子供があるだけの絵の具をひり出して筆先でグチャグチャにかき混ぜた、なんだかよく解らない無秩序な色彩をぶちまけられた様な色合いの芋虫。丸々と肥ったそいつが頭を振り振り背と腹を蠢かし、どこへ行かんとするものか、ノロノロと夏の熱気に暖められたアスファルトの上を這っている…………。 もしもこれを見る者が酷く虫嫌いだとするならば、何にも代えがたい恐怖の具象と化すのであろう。それこそ当の肥った芋虫が彼の体内を数万の群れと化して行進するかの如くに。 だが、その時に我々が感じる不条理としての恐怖を文章という形で完全に伝えることは、おそらく不可能ではないにしても非常に難しい。どんなに言葉を連ねても、描かれた「絵」というそのただ一点の要素をして、見る者に作者の生成したる恐怖――それを共有させるには「文章」というひどく迂遠な媒体は「絵」に勝るものではない。一度に視覚へと注入される情報量は、後者の方が圧倒的だからだ。 そして再び先に挙げた芋虫の比喩を使用するならば、偶然であり突然に遭遇したグロテスクな芋虫は、彼にとって縁もゆかりも因果も無い……言うなればただひたすらに不快感を催さざるを得ない通行者である。そこに人と虫が道端で出会うための関連性を見出すことはできず、ただ嫌悪と恐怖を抱くことのみがその場においては許容され得る。 この、いわば過去からも未来からも完全に隔絶された「ぶつ切り」の情景を表現することが、「不安の種」という作品を真に恐怖たらしめている点なのであろう。 「何故そうなったのかが解らない」「これからどうなるのかが解らない」。それまでの経緯といずれ訪れるであろう結末を完全に排除することによって、ただ主人公に降りかかった災厄をのみ描くことによって、因果なき捻じくれた、日常の断層から顔を覗かせる異形の者たちを召喚することが可能となるのだ。 この作品に描かれている怪物たちや怪現象は、「異形」ではあっても「異界」の存在ではないと思う。我々がこの目で――あらゆるメディアを総動員しても――確認することができる事象というのは世界全体の規模からすればごく限られているのだし、どこかで我々の知らない何かが日々誕生していたとしても決して不思議ではない。 あなたがこうしてこの駄感想を読んでいる間にも、あなたが普段歩く道を、あなたの理解が及ばない「何か」「誰か」が闊歩しているのかもしれないのである。彼らがどのようにして誕生してまたどういった結末を迎えるのか、それを我々が知ることが出来ない限り、現出する恐怖はひたすらに我々を不意打ちし続けるし、これからもきっとそうなのだろう。 その「姿」の情景のみを読者に提示し続けることによって本作に描かれる日常と非日常の断層に住まう者共は不条理たらしめられているし、正体を明かさぬことで、同時に到底その正体を看破し得ない不可解な存在であり続けることが可能なのだ。人間の深い部分に訴えかける「解らない」「判らない」事に基づく恐怖が描かれ続ける限り、視覚を介して思考に根を張るべく、「不安の種」は芽吹くのである。 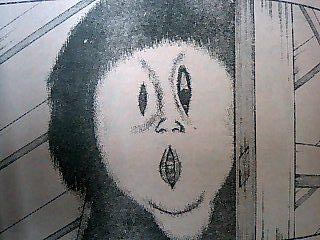 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.07.10 23:37:06
コメント(0) | コメントを書く
[読書] カテゴリの最新記事
|