
|
|
|
カテゴリ:Movie
「カルティエのトリニティリングは、コクトーが制作を依頼してラディゲに贈った」説がいかにアヤシイ話かおわかりいただけたと思うが、この手のネット上の情報のデタラメぶりは枚挙にいとまがない。
だが、プロの著述家の書いたものなら、一般人はごく普通に、正しいと信じてしまうだろう。一般的には、日本ではジャン・コクトー関連の出版物はかなり充実しており、かつ総じて質も高い。 だが、驚くような事実誤認を堂々と垂れ流している「プロ」もいる。 グーグル検索で「ジャン・コクトー ジャン・マレー」と入力したところ、わりあい上の方に出てきた「松岡正剛 千夜千冊『白書』ジャン・コクトー」というエントリー。 フランシーヌ・ヴェズヴェレールやジャン・マレーに関する部分だけ読んでも、間違いのオンパレード、正直ここまでヒドイのは素人のブログでも珍しい。別に著者のメンツをつぶすつもりは毛頭ないのだが、こうしたサイトに限ってコメントもトラックバックも受け付けていない。しかも、どうやらこの千夜千冊という連載は、本にまでなってしまったらしい。印刷物になる時点で誤りが訂正されていればいいのだが、もしそのままだとしたら、これは由々しき問題だろう。 ごく短い文章の中にどれだけ事実誤認があるか、以下に列挙してみよう(青文字が同エントリーからの引用。赤文字が端的な間違い) ブラジル生まれのフランシーヌ・ヴェスヴェレールは、『恐るべき子供たち』のエリザベート役をあてがわれていたとき、スタジオでコクトーに見染められている。 拙ブログを読んでいる方、もしくは映画『恐るべき子供たち』をご覧になった方ならすぐわかると思うが、フランシーヌがエリザベート役をやってるワケがない。正解はフランシーヌの親戚のニコル・ステファーヌだ。 それが『地獄の機械』舞台化のためにしたオーディションで、ギリシア彫像かとも目の眩むジャン・マレーを“発見”したことだった。 さっそく『円卓の騎士』が書かれ、マレーにはココ・シャネルの金と純白の衣裳があてがわれた。 『地獄の機械』はジャン・ピエール・オーモンが主役を演じた1934年の戯曲。コクトーとマレーの出会いは1937年、『オイディプス王』のオーディションだ。『地獄の機械』もオイディプスの話だし、拙ブログでもさんざん書いたように、マレーは『地獄の機械』を非常に気に入っていて、後年何度も再演したので混同したのかもしれない。 また、『円卓の騎士(たち)』はマレーのためにコクトーが書いたものではない。オーモンが初演する予定だったのだが、映画の契約があってできなくなった。そこでコクトーがジャン・マレーに「君が演ってみないか」と声をかけてきた(新潮社『ジャン・マレー自伝 美しき野獣』P63ページより)。 衣装については、「ココ・シャネル担当」と書かれた資料も確かにある。だが、マレーの自伝によれば、衣装をデザインしたのはジャン・コクトーだった。シャネルは生地を提供したらしいのだが、縫製はどこでやったのかははっきりしない。ハクづけのためにシャネルの名前を借りた可能性はあるが、実際のところシャネルがどれほどかかわったのかは不明。 少なくともハッキリしているのは、マレーにあてがわれた衣装をデザインしたのはコクトーだということ。 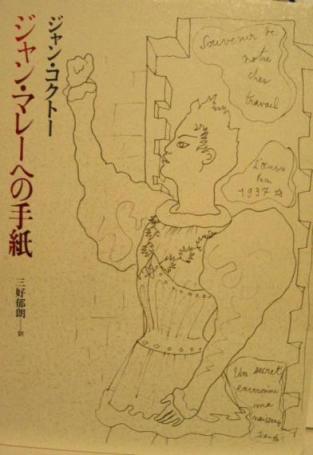 『円卓の騎士(たち)』のためのコクトーのデッサン。マレーの自伝によれば、コクトーはツーロンで、この衣装デザインを練ったという  コクトー原案の衣装をつけた『円卓の騎士(たち)』でのマレーのスチール これ以降、マレーはコクトーが没するまで恋人でありつづけた。どちらも「ジャン!」と呼び合えばすぐ融ける仲だった。ぼくは『ジャン・マレーへの手紙』と『私のジャン・コクトー』(東京創元社)を読んで、ほとんど蒸しタオルを全身にあてられたような気分になったものである 『ジャン・マレーへの手紙』のどのページでもいい、一瞬でも開いてみれば、コクトーがジャン・マレーを「ジャノ」と読んでいたことは誰でもわかる。ジャンと呼び合っていたのはなく、「ジャン」と「ジャノ」と呼び合っていたのだ。 ここから先のコクトーは、1963年に74歳でパレロワイヤルの寝室で死ぬまで、ジャン・マレーをはじめとする男たちと(最後にジェラール・フィリップが加わった) コクトーが亡くなったのは、パリ郊外のミリィ(ミイ)・ラ・フォレの家。発作に襲われたのはサロンだということだ。 コクトーがパリのパレロワイヤル庭園に面したアパルトマン(正確に言えば、モンパンシエ通り36番地)を1940年から亡くなるまで借りていたのは事実だが、パレロワイヤルで死んだわけではない。 最後にジェラール・フィリップが加わった――というのも、よくわからない。確かにコクトーはフィリップを評価していたし、ロケを見に行ったりしている。だが、たいした交流はない。フィリップはマレーから申し込まれたコクトーの映画『オルフェ』への出演を断わっている。コクトーとの関わりの深さにおいて、フィリップとマレーとを比べられるものではないし、それにフィリップは別に「最後」ではない。フィリップと知り合ったあとに、もっと若いアラン・ドロンがコクトーのもとにみずから売り込みに来ている。 ラディゲに関してもヘンな記述がある。 1919年、16歳の邪悪な天使、レイモン・ラディゲが登場する。それからコクトーはラディゲを精神嬰児のように体中でもペニスでも偏愛しつづけた。それがどういうものであったかは本書『白書』の中のスケッチを見てもらうのがいい。 本書というのは、求龍堂から出ている『白書』のことだが、訳者である山上晶子氏が書いているように、ここに挿入されたエロティックなスケッチは、『白書』(1928年)のためにコクトーが描いたものではなく、1946年にジュネの『ブレストの乱暴者』たちのためにコクトーが療養先で描いたものやコクトーが1940年にモンパンシエ通りに移って以降に描いた未発表の素描を、コクトー没後に編集者が集めて入れたもの。『白書』執筆時とこのスケッチを描いた時期は相当に離れており、かつ直接的には何の関係もない。 だから、『白書』の挿絵をラディゲと結びつけるのは無理がある。ただし、『白書』に描かれたHと私との関係が、1923年に亡くなったラディゲとコクトーの関係を強く想起させるものであることは確か。 コクトーとマリー=ロール・ド・ノアイユおよびナタリー・パレとの関係にも誤解と混乱がある。 マリー(ロール・ド・ノアイユ)が紹介したナタリー・パレは、そのとき27歳。婦人服デザイナーのリュシアン・ルロンの妻だったが、やはり血が凄かった。父親はロシア皇帝アレクサンドル3世の弟だ。しかも皇帝と弟(ナタリの父)はともにボルシェビキによって暗殺されていた。高貴な家柄が没落して美しい。コクトーはこういう条件には、もう、なにがなんでも目がなかった。マリーは絶世の美女で、肌が透き通っていた。コクトーは夢中になり、たちまち妊娠させ、堕ろさせた。コクトーはナタリーのことを「輝くシャンデリアを必要とする驚くべき植物だ」と書いている。その植物の花芯に灼かれたのだ。 赤文字のマリーはナタリーの単純ミス。コクトーの子を妊娠した(と少なくともコクトーが信じた)のはナタリー・パレのほう。また、コクトーが堕ろさせたのではなく、ナタリーのほうが「(ロシア王朝の)ロマノフとコクトーの血が混ざるのが怖い」と言ってスイスで堕胎してしまった。コクトーはこのことにひどく傷つき、10年後に書いた『占領下日記』でそのときの苦悩を吐露している(詳しくは拙ブログ4/19のエントリー参照)。これを読めばコクトーが堕ろさせたのではないことは明らか。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008.10.12 18:08:24
[Movie] カテゴリの最新記事
|