パオロ・コニェッティ 「帰れない山」(新潮クレストブック) 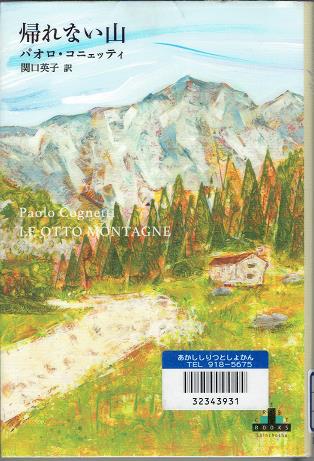 読み終えて、切ないとしかいいようがない、ある感じにとらえられてしばらく座り込んだ。涙をこぼしていたかもしれない。年を取ったのだろうか。
読み終えて、切ないとしかいいようがない、ある感じにとらえられてしばらく座り込んだ。涙をこぼしていたかもしれない。年を取ったのだろうか。
山に登ることを生きていることの証しのように暮らしている父親と父に連れられて山に登り始める少年の独白が小説の始まりであり、やがて、数十年の時が経ち、死んだ父が、かつての少年に語った「人生には時に帰れない山がある。」という言葉を思い出して小説は終わる。
小説の邦題はここからとられているようだが、原題は「Le Otto Montagne」。たぶん「八つの山」というくらいの意味ではないかと思うが、その題名の由来も読めばわかる。
作家自身が、実際に経験した出来事が、自伝的に描かれていると感じさせる作品だが、語り手である「僕」と家族との関係という経糸(たていと)と、町の少年であった「僕」が山の村で出会った山の少年「ブルーノ」との交友という緯糸(よこいと)で織られたテクスチャー=織物であるかのように小説は出来上がっている。
中でも「トムソーヤ―とハックベリー・フィン」の組み合わせのような、この二人の少年の物語の世界は、昨年(2018年)亡くなったエルマノ・オルミの傑作映画「木靴の樹」の世界を彷彿とさせる。
あの映画もこの小説と同じ北イタリアのアルプスのふもとの村が舞台なのだから、当たり前といえば当たり前なのかもしれないが、描かれた時代には、半世紀ほどのずれが歴然とあるはずだ。
にもかかわらず、現代社会から取り残された山の村の、貧しい農夫の息子ブルーノと都会のインテリの一人息子「僕」が出会い、兄弟のような友情で結ばれ、やがて別れる世界は、あの映画のさみしい村の風景や農夫や子供たちの姿に重なり、貧しく、美しく、哀しい。
加えて、この小説が北イタリアのアルプスの山並みを背景にして繰り広げられていることは、この作品を語るうえで忘れてはならないことだろう。読者にとって、この風景の描写は、この作品の特筆すべき魅力だと思う。
僕たちは山頂に座り、持ってきたパンとチーズをかじりながら雄大な風景に見惚れていた。モンテ・ローザのどっしりとした山群が、山小屋やロープウェイ、人工湖、マルゲリータ小屋から降りてくる登山者の隊列まで識別できるほど間近に迫っていた。父はワインの入って水筒の蓋を開け、午前中は一本と決めていた煙草に火をつけた。
「この山は薔薇色だからモンテ。ローザという名前がついたわけじゃないんだぞ。」と父は蘊蓄を語りだした。
「氷という意味の古語が語源になってるんだ。つまり氷の山だ。」
それから父は、東から西へと順に四千メートル峰の名を挙げていった。毎回決まって最初からくりかえす。実際に登る前に、一つひとつの頂を正確に把握し、長い間憧れを抱き続けることが肝要なのだ。
ジョルダ―ニの控えめな頂、それを上から見下ろすピラミッド・ヴィンセント、ピークに大きなキリスト像が立っているバルメンホルン、稜線があまりに緩やかでほとんど目立たないパロット、さらにはニフェッティ、ズムスタイン、デュフールと、気品の漂う鋭い峰が三姉妹のように並んでいる。次いで、「人食い尾根」と異名をとる尾根で結ばれた二つの頂上を持つリスカム、その隣の双子の山は、優雅な波を描いているのがカストルで、気の荒そうなのがポルックスだ。そしてロッチャ・ネーラの輪郭に、無垢な表情のプライトホルンが続き、一番西には孤高のマッターホルンが屹立している。
父はこの山を、まるで年のいった伯母さんかなにかのように、親しみをこめて「偉大な尖峰」と呼んでいた。一方、南の平野の方角は全くといっていいほど見ようとしなかった。平野には八月の靄が立ちこめている。あの灰色のフードの下のどこかに炎暑のミラノの街があるはずだった。
絵巻物を広げるようにして、繰り広げられる山々の連なる風景描写は、それだけで、山になんて何の関心もない読者をひきつける山岳小説のおもむき十分だが、それだけではない。このアルプスの、一つ一つの山の風景は登場人物たちの心に織り込まれ、それぞれの心模様を作っていて、彼らの生き方をリアルに語るうえで、欠かすことのできない背景となっていることを読み手は実感することになる。そういう意味で、真の山岳小説といえるかもしれない。
「子供時代の山」と題された「僕」とブルーノとの少年時代の生活。青年になった僕と父との、葛藤と和解の物語を描いた「和解の家」。最終章「友の冬」は父亡き後、中年に差し掛かった「僕」とブルーノとの再会と別れを描いている。
中年に差し掛かった語り手、僕の、一見、「自伝風」、「私小説風」の回想は、上記のように章立てされた三つの時間をたどりながら、父やブルーノと登った幾多の山を登り直すことから始まり、アルプスのふもとの山の村の母との生活や家族の思い出を丹念に描きながら、とうとう「帰れない山」が聳えている場所にやってきて、結末を迎える。
「帰れない山」とは何なのかは、読んでいただくほかないが、それが小説の主題を暗示している比喩であることは間違いない。
ここまで読んでいただいて、ある種、「山と人生」とでもいうべき人生論物語風の結末を予想する人もいるかもしれない。残念ながら、その予測は完全に外れている。
この作品が「人生」を定型化することを目論んで書かれた小説ではないことは、お読みになればしびれるような余韻とともに、実感として理解されるにちがいないだろう。
乞う、ご一読。 (S) 追記2019・05・03
「父と子」、「母と子」、「家族」、「友情」・・・。この小説から読者が感じ取るイメージのパターンは古典的です。まあ、ありきたりといってもいいかもしれません。しかし、読み終えてみると、どこかに、ある「新しさ」があって、それが多分この小説の魅力なのだと思う。その新しさを解説できれば、プロの書評ですが、残念ながら、ボクにはうまく言えませんね。
追記2023・04・27
なんと、映画化されたらしい。まだ見ていないのですが、とりあえず記事の修繕を、と、考えて触りました。映画が楽しみです。
追記2023・05・16
映画を見てきました。感想は別に書こうと思いますが、ボクが小説を読んで感じていた「新しさ」を、映画製作者は感じなかったようで、悪くはないのですが、かなり古典的な青春葛藤ドラマとして描かれていて、ちょっと拍子抜けでした。
うーん・・・
という感じでしたね(笑)
ボタン押してね!
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村








