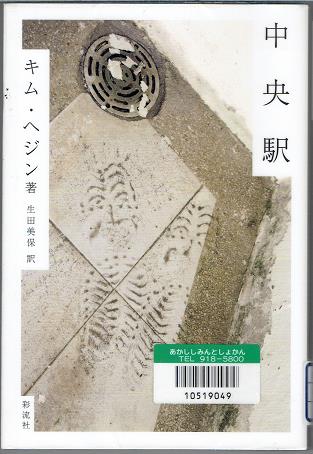キム・ヘジン 「中央駅」(彩流社)
「打ち捨てられた人間」といういいかたがあります。「アウシュビッツの囚人写真家」という小説を読みながら、その本に掲載された写真や、主人公の淡い恋の物語の中でに、人間」を回復しようとする登場人物たちの絶望的な姿を見つけ出し、考え込んでいる「気分」に浸っているぼくに強烈な「ノー」を突き付けてくる小説をと立て続けに二冊出会いました。
一冊がチョ・ナムジュ「82年生まれ、キム・ジョン」(筑摩書房)、もう一冊が本書、キム・ヘジン 「中央駅」(彩流社)でした。
二冊とも韓国の若い女性作家によって書かれているのですが、前者については既に感想を書いたので、きょうは「中央駅」を案内したいと思います。
二つの小説に共通していることがもう一つあります。「82年生まれ」は「名前のない男」が書いた日記でしたが、この作品も「名前のない男」について書かれた物語でした。
「82年生まれ」では、語り手は作家から「名前」を剥奪されていた趣でしたが、この作品では「人間」としてふるまうために最後に残った財産である「身分証明書」=「名前」を売り払うことで「人間」であることをやめてしまう話です。
一人の青年が「中央駅」の駅前広場を歩いています。ここが彼の棲家になって、まだそれほどの時間がたっているわけではなさそうです。
作家の「あとがき」によればソウル駅ということらしいですが、韓国もソウルも知らないぼくにとって、中央駅は中央駅にすぎません。駅前広場はホームレスの生活の場ですが、そんなこととはかかわりなく、この駅でも再開発が進んでいます。
男はキャリー・バッグ一つに詰め込んだ財産を引きずりながら一日中この広場をグルグル歩き続けます。日が暮れてたどり着いた場所が今夜の彼の家です。そこで、一番かさの高い家財道具、段ボールの寝具を広げます。
この男の視線によって世界を捉え、世界に対するこの男の意識が一人称「俺」によって語られています。
文章は率直で怒りと自己嫌悪を漂わせていますが、下品ではありません。
「現在形の直線的な文章で断崖絶壁に追い詰めては平地に連れ戻すような文体」
訳者の生田美保は「あとがき」で、こんなふうに評していますが、ぼくは、中上健次の「十九歳の地図」を思い浮かべながら、「青春小説」という印象で読み進めました。
男は、ある日、一人の女と出合います。女が男に対して最初にしたことは身体を差しだすことでした。二つめにしたことは寝入った男の全財産であるキャリー・バッグを盗み出し、それを酒に変えることでした。
一夜の逢瀬で姿を消した女を男は探し回ります。再会した二人がしたことは、互いの体を相手に差しだすことでした。
その行為のなかで、女にとっては寒さをしのぐための、男にとっては刹那的な欲望の処理のための、それぞれの肉体が道具として「交換」されていくようにみえます。
社会で生きている人間であることの残滓を捨てきれない男は、行為の果てに、女の来歴と名前を知りたがります。もちろん、彼には、まだ、自らの「身分証明書」を捨てることができません。
「私だってアンタのことは知らない。どうしてここにいるのか、何か犯罪を犯したのか、詐欺にあったのか、何ひとつ知らない。それでも、私はあんたのことが好き。それでいいじゃないの」(P110)
「そうよ。私はあんたが期待しているような、そんな人間じゃないわ。いったい、こんなところで私にどう生きてほしいの。」(P111)
家族を捨て、住み慣れた町を捨て、この広場で暮らし続けた女は生活の糧であった体を病気によって失いつつあります。とうとう、女は死に瀕した体の治療に必要な「身分証明書」を手に入れるために、かつて暮らした町を訪ねます。
付き添った男は「町」が女を捨ててしまっていたことを確認しただけでした。
「ずいぶん変わっている。あの頃はこんなんじゃなかったのに」
女はどちらに進むことも出来ずにその場に立ち尽くす。すぐに方向感覚を取り戻すだろうと思っていたが、何歩か歩いては立ち止まってを繰り返している。俺は、横断歩道の信号が変わって人々が急いで渡って行く様子を見ながら、ボンヤリと突っ立っている。(P226)
「肉体」を、いや、「生命」を失いつつある女を救うために、男は、最後まで執着していた「名前」を売り「カネ」を工面します。しかし、手に入れた「カネ」もその夜のうちに盗まれ、結果的に「肉体」以外のすべてを失い、女の傍らに座り込みます。
目の前には腹水でスイカのように膨れ上がった体を抱えて眠るように横たわっている女がいるだけです。
広場の花壇の植え込みの陰で女の体をさすり続ける男がいます。いつの間にかというべきでしょうか、つながりを最後まで担保するはずの「言葉」も「肉体」も失いながら、ホームレスの男と女が「人間」の姿を取り始めます。
さすり続ける乳房の手触りと、乳房に当てられている手の感触のほかには何も残されていません。
とうとう、何もかもを亡くしてしまった所に小説はたどり着いたという納得が、読者のぼくの中で広がってゆきます。
それは「愛」と呼ぶには、あまりにも荒涼とした世界ですが、思い浮かんでくる、例えば、ノラ猫の親子の仕草とは一線を画している要素が一つだけあると思いました。それは「Still Human=それでも人間」ということです。
「何もかも亡くした状況でも、我々は自分以外の誰かを愛することができるのかを問いたかった。」
作家がインタビューに答えた言葉だそうですが、人間が「何もかも亡くす」という様子を見事に描いた作品だと思いました。結末で「男」は、もう一つ、何かを亡くしてゆくのですが、それは作品を読んでお確かめください。
30代の作家の「才能」と「可能性」、社会と人間に対する視線の鋭さを感じさせる作品でした。
追記2020・08・01
チョ・ナムジュ「82年生まれ、キム・ジョン」(筑摩書房)の感想は書名をクリックしてください。

 ボタン押してね!
ボタン押してね!
 ボタン押してね!
ボタン押してね!