
|
|
|
「100days100bookcovers no20」(20日目)
『海辺の王国』ロバート・ウェストール作 坂崎麻子訳 徳間書店 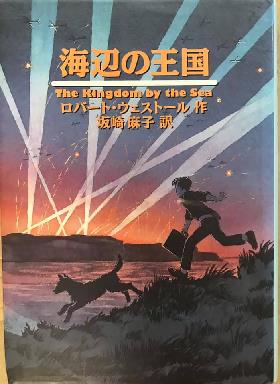 SODEOKAさんが選んだ小泉八雲の『骨董・怪談』から、KOBAYASIさんはどこに飛ぶのかしら?八雲が蚊に転生して、虚子を食った松江?明治の東京?ギリシア?アイルランド?カリブ海?全然見当をつけられず、準備するのは諦めていました。 SODEOKAさんが選んだ小泉八雲の『骨董・怪談』から、KOBAYASIさんはどこに飛ぶのかしら?八雲が蚊に転生して、虚子を食った松江?明治の東京?ギリシア?アイルランド?カリブ海?全然見当をつけられず、準備するのは諦めていました。 KOBAYASIさんが選んだのはアイルランドだったのですね。素敵な紹介文ですね。大人の哀愁を感じる藤原新也の写真の紹介といい、アイルランドは文学の宝庫ですもの、一昨日から盛り上がっていますね。 映画の話題も掘れば掘るほどザクザク出てきますし。クリント・イーストウッドも『ミリオンダラー・ベイビー』で孤独で気骨のあるボクシングトレーナーの役を、アイルランド系として演じていますね。 アイルランドに離れがたいものを皆さん感じてらっしゃるようですが、私は残念ながら、アイルランド文学も、アイリッシュパブも、アイリッシュダンスも無縁で生きてきました。ギネスってビールは好きですが。 仕方がないので今日は、『風のフリュート』が吹くアイルランドの西海岸『ディングルの入江』からスコットランドの東海岸ノーサンバーランドへ出かけたいと思います。 もうお読みの方も多いと思いますが、ロバート・ウェストールの児童文学『海辺の王国』を選びました。(もう2週間前から想像がついてたって?) 彼はイギリスの児童文学のために設けられたカーネギー賞やガーディアン賞などをいくつもとっていて、今でも子どもにも大変人気があるそうです。私も好きな作家で、『かかし』『クリスマスの幽霊』『弟の戦争』『ブラッカムの爆撃機』『青春のオフサイド』とか読んでますね。読みやすいから。 こどもの時に第二次世界大戦を経験し、大人になってからは美術の先生をしていたそうです。自分の一人息子に戦争中の体験を話したことがきっかけで小説家になったということですが、この息子さんは18歳のときにバイクの事故で亡くなったそうです。『海辺の王国』には、子どもを失くした人物が出てきますが、作者自身を投影しているように感じました。 では、この小説を紹介します。第二次世界大戦中のノーサンバーランドの町に、ハリーという名前の十二歳の少年がいました。ドイツ軍の空襲に遭い、いつものように防空壕に逃げ込んで気づいたら、自分ひとり、家もこわれ、家族はみんな死んだと知らされます。 一人ぼっちでとにかく雨露をしのげるところをもとめてさまよいます。人目につかない海辺で壊れた木製の船をみつけ、そのボートを裏返しにしてもぐって夜を過ごします。寂しさと真っ暗な夜がばけもののようで怖くて涙が止まりません。 すると痩せた汚れた犬がやってきます。おそらくこの犬も飼い主が空襲に遭ったのだろうと思い、一緒に夜を過ごしてからドンと名付け、相棒としてさまざまな経験を重ねてゆきます。 警察だと名乗るチンピラに襲われたり、勝手に農家の納屋に忍び込んで寝ていたら見つかり、あやうくその農夫を殺しそうになったり。今でいえばホームレスの男のそばで、海に流れ着くものを拾い命をつないだり。あわやレイプ。もう死ぬ。ということもあったりしながら、少年は自分で生きる力や人を見る眼を身につけていきます。 マーガトロイドという興味深い人物が登場します。彼は動物と共に生き、まるで人間を相手にしているように会話します。けれど、人間相手だと硬くなってどうかすると言葉も交わせなくなる狂人の風情さえあります。彼は子どもを失くしていたのです。 村人は彼を気の毒だがもはや変人としてしか見ませんし、本人もそれを望んでいるようでしたが、ハリーと出会い、ともに暮らすことで柔らかい心を取り戻します。大人に助けられていた少年が傷ついた大人を癒すところも心が温かくなります。 そして、なんと、死んだと知らされていた家族はみんな生きていました。再会できたのです。が、全然、よくないのです。 家族は「胸がわるくなるような」家にいて、「みすぼらしい」「怒り狂った」「居丈高」で「自分たちだけが苦労してきたんだと、自分をあわれむばかりの……せまい、せまい世界」の住人だという現実に直面する羽目に逢います。 今まで読んできた児童文学と真逆です。最も会いたかった家族が実はこんなつまらない人だったとは‼︎彼は 「これからさき、どんなに長いあいだ、本心を見せずにすごさなければならないか……」 と考えて暗澹としますが、けれど、いつか、かならず 「広々した空気があって、陽があたり、ドンがいる、ノーサンバーランドの海辺」「自分で見つけた、いや、自分で作ったハリーの王国」「海辺の王国にかえりつこう」 と思うのです。 実は子育て中にこの本を読んで私自身はこの皮肉な終わり方にショックを受けました。 混乱していましたが、その後、「友情とか家族とかふるさととかは、なにより守るべきもので、誰もが最後に戻りたいところだ」というのはステロタイプだったということに気がつきました。家族って狭いところに子どもを閉じ込めておく装置でもあるのですね。 親は、子どもだけが自由で大きな権利を持つことに嫉妬してしまうかもしれない。それぞれの人間が偶然、親になったり子どもになったりして、相性が合えばいいけれど、そうでないことも当然あるはず。 自由と寂しさ、不自由と愛情は切り離せないことを受け止めるしかないという、諦めというより勇気に近いものが自分の中にもあることに気がつきました。さまざまなものに皮肉な目を持つ勇気、家族があろうとなかろうと孤独であることや、世間が不条理という以上に自分自身が不条理な生き物だということに直面するしかない。それでも生き延びようとすることが正しいことで、そうするしかないと思いました。 最後にスタジオジブリの宮崎駿は引退会見した時にウェストールについて触れた言葉を借りて挙げておきます。 僕が好きなイギリスの作家にロバート・ウェストールがいて、作品の中に自分のかんがえなければいけないことが充満しています。この世はひどいものである。その中で『君はこの世で生きていくには気立てが良すぎる』というセリフがあります。これは少しも誉め言葉ではないんです。それでは生きていけないぞと言っているのです。それに胸を打たれました。と言っています。 日本でも湾岸戦争の後で『弟の戦争』が翻訳されて、中高生の読書感想文対象として話題にもなりました。原題は“Gulf”で、「湾、入江」です。KOBAYASIさんからなんとか繋げられたとはおもうのですが、SIMAKUMAさんはそう来るだろうと予想されていたのでは?どうぞ、お次をよろしくお願いいたします。(E・DEGUTI2020・06・18) 追記2024・01・20  にほんブログ村 にほんブログ村  
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.01.29 23:37:44
コメント(0) | コメントを書く
[読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ] カテゴリの最新記事
|