
|
|
|
カテゴリ:読書案内「翻訳小説・詩・他」
100days100bookcovers no87 87日目
ルシア・ベルリン「掃除婦のための手引書 ルシア・ベルリン作品集」(岸本佐知子訳 講談社文庫) 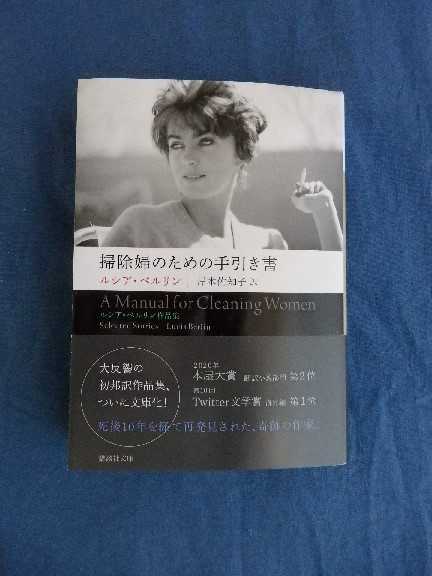 こういう「古典」は大概読んでいないのだけれど、『雪国』は何かのきっかけで読んだ記憶は一応あった。あったけれど、駒子というヒロインと名前くらいしか覚えていなかった。 SODEOKAさんの紹介文で、物語のラストあたりは思い出したが、それももしかしたら映像で観た記憶と重なっているやもしれず、読書の記憶かどうかは判然としない。 どういう接続をしようかと考えていて、コメントに中に三島の名前が出てきたのを思い出した。検索してみたら、川端がノーベル文学賞を受賞した年に三島も候補に挙がっていたという話だった。三島は、仕事絡みで一部を読んだことを除けば、未だにまともに読んだことがない。学生のときに一学年上の先輩(DEGUTIさんですけど)に「国文科に来る男で三島を読んだことないとかいうのはおまえくらいや」と言われたのを覚えている。 いや、ほんとに文学には縁が、あまりというかほとんどなかったのだ。では何で国文科を選んだのかという話はここではしないが、ああそういえば、と思い出した。 三島の小説は読んでいないけれど、「三島」の名前が出てくる小説は近頃読んだ。『雪国』とは直接はまったく接点はないのだけれど、この際、ご容赦いただくとして。 『掃除婦のための手引書 ――ルシア・ベルリン作品集』ルシア・ベルリン 岸本佐知子訳 講談社文庫 この文庫を読むきっかけになったのは、twitterで訳者の岸本佐知子のアカウントをフォローしている関係で、2019年7月にこの文庫の親本が出たときから情報をずっと得ていたことである。 今年3月に文庫になって、おもしろそうだなと改めて思って、久しぶりに文庫ながら新刊を買った。 原題は"A Manual for Cleaning Women : Selected Stories by Lucia Berlin"。 「訳者あとがき」によれば、作家は1936年アラスカ生まれのアメリカ人で2004年没。生涯に76の短編を書いた。1977年に世に出た初めての作品集"A Manual for Cleaning Ladies"により、一部には名を知られる存在になったが、生前も死後も「知る人ぞ知る」作家だった。しかし2015年、全作品から43編を選んだ作品集"A Manual for Cleaning Women"が出版されて事態は変わる。その年の雑誌新聞の年間ベストテンリストのほぼすべてを席巻。 この邦訳版は、その2015年の作品集から24編を選んだもの。残りの19編は、今年4月『すべての月、すべての年』として出版された。 作家は、鉱山技師だった父親の関係で、幼少期はアイダホ、ケンタッキー、モンタナなどの鉱山町を転々とする。5歳のときに父親が第二次大戦に出征、母と妹とテキサスのエルパソにある母の実家に移り住む。歯科医の祖父は酒浸り、そして母も叔父もアルコール依存症。終戦後、父が戻ると、チリのサンチャゴに移住、18歳でニューメキシコ大学に進むまでチリで過ごす。エルパソの貧民街から召使い付きのお屋敷暮らしへ。 大学在学中に最初の結婚、2人の息子をもうけるがその後、離婚、58年にジャズピアニストと2度めの結婚、ニューヨークに住む。さらにジャズミュージシャンだった3番めの夫と61年からメキシコで暮らし、2人の息子を授かるが、夫の薬物中毒等により離婚。ベルリン姓は3番めの夫の姓とのこと。 71年からカリフォルニアのオークランドとバークレイで暮らし、学校教師、掃除婦、電話交換手、ER(救急救命室)看護助手等をこなしながら、4人の息子を育てる。このころから自らアルコール依存症に苦しむ。 小説は20代から書いていて、24歳でソール・ベロー主宰の雑誌ではじめて作品が活字になった。その後、文芸誌に断続的に作品を発表。85年には今回紹介する作品集所収の「わたしの騎手(ジョッキー)」がジャック・ロンドン短編賞を受賞。 90年代以降、アルコール依存症を克服後はサンフランシスコ郡務所等で創作を教えるようになり、94年にはコロラド大客員教授に。准教授にまでなるが、子供の頃から患っていた脊椎湾曲症の後遺症等が悪化、酸素ボンベが手放せなくなる。2000年大学をリタイア、2004年癌で死去。 と、バイオグラフィーを書き連ねたのは、作品がほぼすべて作家のこうした経歴や経験を基にしているからだ。 たしかに題材を採りたくなるような波乱に満ちた家庭環境や経歴、経験に思える。 素直に考えれば、そこに作家が創作上の「リアリティ」の源泉ないし支点を求めたということだ。あるいは、経験以上に「リアル」な物語を紡ぎ出すほど「器用」ではなかった。 小説は、短いものは2ページに満たないものから、長くても23ページほど。読んでみてわかる、この作家の最大の特質は、やはりその「表現」であり言葉の選び方だ。「訳者あとがき」で訳者が使う用語を使うなら「声」ということになる。多少曖昧な表現に変えるなら「文体」ということになるのかもしれない。ただ、原文は英語なので、訳者を通した上での「声」であり「文体」ということになる。 「強い」状況を「強い」言葉で表現しながら、そこにユーモアや得も言われぬ叙情性や詩情が浮かび上がる。散文が詩に変わるときがある。 自身のことを描いても、そこには自らや状況を突き放したような「透徹」で「リアル」な距離がある。これは出来事と、執筆された時間と場所に実際に「距離」があるということだけに由来するものではない、おそらく。 いくつか紹介する。(なお、まとまった引用は、>引用部分<で示す。) まずは、「三島」が登場する「わたしの騎手(ジョッキー)」。「わたし」はER(救急救命室)看護助手。 >わたしがジョッキーを受け持つのはスペイン語が話せるからで、彼らはたいていがメキシコ人だ。はじめてのジョッキーはムニョスだった。まったく。人の服なんてしょっちゅう脱がしていうるからどうってことない。ものの数秒で済んでしまう。気を失って横たわるムニョスは、ミニチュアのアステカの神様みたいに見えた。乗馬服はひどく複雑で、まるで何かの込み入った儀式をしているようだった。あんまり時間がかかるので、めげそうになった。三ページもかかって女の人の着物を脱がせるミシマの小説みたいだ。(中略)長靴は馬糞と汗の匂いがしたけれど、柔らかくてきゃしゃで、シンデレラの履きもののようだった。彼は魔法をかけられた王子様みたいにすやすや眠っていた。 比喩が少なくない。この作品集全体に言えることだが、特にこの掌編はそういう傾向がある。しかし「ジョッキー」という存在が、初めて見て触れるものみたいに描かれた作品には、新鮮な驚きと慈しみが感じられる。 そして、作品集中最も短い「マカダム」。 >まだ濡れているときはキャビアそっくりで、踏むとガラスのかけらみたいな、だれかが氷をかじってるみたいな音がする。 おそらくは子供の頃に転々として住む場所を変えていたことや家庭環境に関わりがあるのだろう、孤独な子供の肖像が静かに描き出される。 ちなみにこの「マカダム」、調べてみると実際に人の名前だったことがわかった。ジョン・ライドン・マカダム。作家はそれを知っていたのだろうか。 歯科医の祖父のことを書いた「ドクターH.A.モイニハン」では、歯科医の祖父が、自身の歯を総入れ歯にするために、「新しい連中」のやり方によって、前もって型を取って作った義歯を入れるために歯を抜くという「ホラー」が描かれる。 ウイスキーを飲みながら、祖父が自分の歯をペンチで抜き始める。(おそらく)小学生の「わたし」にも手伝わせる。 >祖父はわたしの頭ごしにウイスキーの瓶をつかみ、らっぱ飲みし、べつの道具をトレイから取った。そして残りの下の歯を鏡なしで抜きはじめた。木の根をめりめり裂くような音だった。冬に地面から木を力ずくでひっこぬくような。血がトレイにしたたり落ちた。わたしがしゃがんでいる金属の台にも、ぽた、ぽた、ぽた。 それから、祖父はわたしに「抜けえ!」と言う。祖父はやがて気を失う。 >わたしはその口を開けて片方の端をペーパータオルを押し込み、残りの奥歯三本を抜きにかかった。 この、「臨場感」というか、感覚的に迫ってくる感じは恐ろしいほど。にもかかわらずユーモアも漂う。 そして表題作「掃除婦のための手引書」。 路線バスの番号別に、それぞれの家に赴く一人の掃除婦の独白の形式。所々で、ターと呼ばれる死んでしまった夫ないしボーイフレンドのことが語られる。 >ある夜、テレグラフ通りの家で、ターが寝ていたわたしの手にクアーズのプルタブを握らせた。目を覚ますと、ターはわたしを見下ろして笑っていた。ター、テリー、ネブラスカ生まれの若いカウボーイ。彼は外国の映画を観にいくのをいやがった。字を読むのが遅いのだと、あるとき気がついた。 >ターは絶対にバスに乗らなかった。乗ってる連中を見ると気が滅入ると言って。でもグレイハウンドの停車場は好きだった。よく二人でサンフランシスコやオークランドの停車場に出かけて行った。いちばん通ったのはオークランドのサンパブロ通りだった。サンパブロ通りに似ているからお前が好きだよと、前にターに言われたことがある。 好きだった男を「ゴミ捨て場」に喩える例はたぶん他に知らない。しかも、その後を読むと、彼女の感じるターの魅力が伝わってくる。 さらに、いろんな意味で作家に大きな影響を与えたと思しき母親を書いた「ママ」は、メキシコシティで暮らす、末期ガンの妹サリーとの会話を中心にしている。 >母は変なことを考える人だった。人間の膝が逆向きに曲がったら、椅子ってどんな形になるのかしら。もし、イエス・キリストが電気椅子にかけられたら?そしたらみんな、十字架のかわりに椅子を鎖で首から下げて歩きまわるんでしょうね。 >「愛は人を不幸にする」と母は言っていた。「愛のせいで人は枕を濡らして泣きながら寝たり、涙で電話ボックスのガラスを曇らせたり、泣き声につられて犬が遠吠えしたり、タバコをたてつづけに二箱吸ったりするのよ」 いや、この部分がどの程度「事実」に基づいているか、あるいは内容の「妥当性」はいかほどかを別にして、この「切れ味」は相当なものだ。 これが作家の実際の母親の発言に近いとしたら、この母にしてこの作家というところは確かにある。訳者の作家を評する言葉を借りれば「冷徹な洞察力と深い教養と、がらっぱちな、けつをまくったような太さが隣り合わせている」。 他に、アルコール依存症の自身を題材にとった「最初のデトックス」「どうにもならない」「ステップ」では、「悲惨」な状況をしかし淡々と描くことによってかえって日常の切迫感が浮き彫りになり、サンフランシスコ群刑務所で創作を教えた経験に基づいた「さあ土曜日だ」では、一人称を服役囚にして、自らが経験した「先生」も登場させるのだが、悲しいラストも含めて「小説」としてとりわけ印象に残る。 あるいは、三番めの夫との出会いと別れが回想される「ソー・ロング」も、わずか15ページほどで過去と現在が映像的なイメージで見事に交錯する。 もしかしたら、映像喚起的というのもこの作家の特質の一つかもしれない。作家には、「大丈夫」ではない自身やその周囲を観察し、想起し、認知する視線がいつもある。感情的にも不安定で愚かしい行動に走る自身をそして周囲を、肯定するのではなく「自覚」し「認知」している。 繊細で鮮やかな描写も、そこから始まる。だからどんなに苛烈な場面や物語でも、どこかに「優しさ」に似たものを感じる。 最後に翻訳について。原文の英語がわからないし、わかったとして翻訳の良し悪しを判断する力量などないので単なる印象になってしまうが、岸本佐知子の翻訳はすばらしいと思う。 では、DEGUTIさん、次回、お願いいたします。T・KOBAYASI・2022・06・30 追記2024・05・16 投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目)(51日目~60日目)(61日目~70日目)(71日目~80日目) (81日目~90日目) というかたちまとめ始めました。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと備忘録が開きます。   
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.05.22 14:11:01
コメント(0) | コメントを書く
[読書案内「翻訳小説・詩・他」] カテゴリの最新記事
|